一言で「夢の酒」を解説すると…

旦那が夢で見た話に嫉妬して、代わりに大旦那が夢に喝を言いに行った噺。
主な登場人物

旦那の見た夢を見て、嫉妬したお花です!

美人な女と一緒に酒を飲んだ夢を見た旦那です!

二人のやり取りに呆れて、自分が夢に入って喝を入れようとした大旦那です!
夢の酒の詳細なあらすじ
梅雨の昼間、大黒屋の若旦那がうたた寝をして夢を見ていた。
目を覚ました若旦那は、夢の内容を女房のお花に話す。夢の中で、若旦那は向島で美しいご新造さんと出会い、酒を飲み、色っぽい雰囲気で過ごしていたが、お花に起こされてしまった。
この話を聞いたお花はやきもちを焼き、大旦那に若旦那の「浮気話」を告げ口する。大旦那は「夢の話だから泣くことはない」とお花を諭すが、お花は「日頃からそう思っているから夢に出る」と納得せず、大旦那に向島の家へ行って文句を言ってくれと頼む。
困った大旦那は、淡島さまの上の句を詠みあげて寝れば夢に入れるという話を聞かされ、無理やり寝かされる。夢の中で大旦那は向島の家に行き、酒を勧められるが、冷や酒は嫌だと断っているうちにお花に起こされる。
大旦那「惜しいことをした」
お花「お小言をおっしゃろうというところをお起こし申しましたか?」
大旦那「いや、冷やでもよかった・・・」
夢の酒を聞くなら
夢の酒を聞くなら「桂文楽」
桂文楽の「夢の酒」は、幻想的な物語と深い人情味が心に残る一席です。夢の話でありながら、お花の嫉妬心が笑いを誘うユニークな展開が魅力です。文楽独特の語り口で、夢と現実が交錯する世界を鮮やかに描き出します。
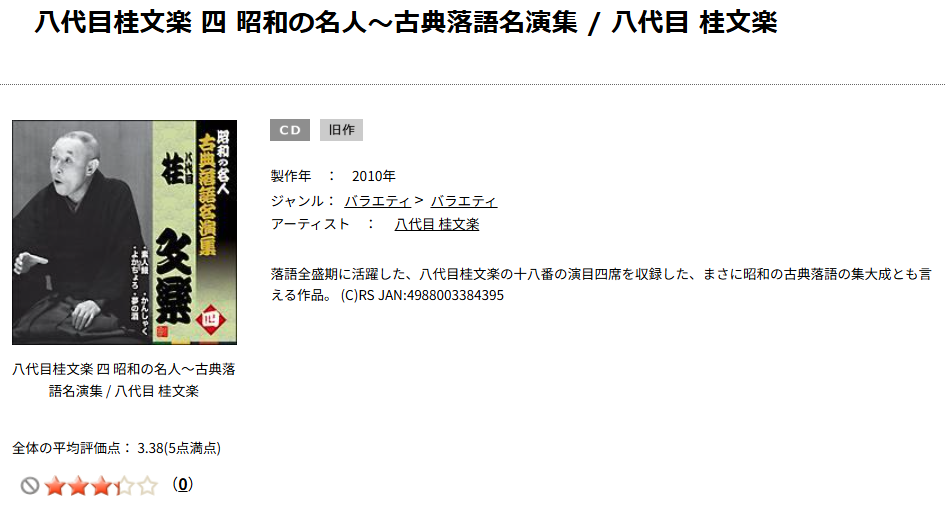
画像引用:TSUTAYA DISCASより
江戸時代の「夢」に関する風習や迷信

「夢の酒」では、夢の中での出来事が現実にも影響を与え、登場人物が振り回される様子が描かれます。江戸時代の人々にとって「夢」はどのような存在だったのか? 夢に関する風習や迷信を深掘りしてみましょう。
1. 夢は「未来を占うもの」
江戸時代、人々は夢を単なる脳内の出来事とは考えず、「神仏からのメッセージ」「未来の出来事を暗示するもの」として捉えていました。特に重要視されたのが「初夢」です。
① 初夢と「一富士二鷹三茄子」
- 新年最初の夜に見る夢を「初夢」といい、これがその年の吉凶を占うとされました。
- 「一富士二鷹三茄子」が出てくる夢は縁起が良いとされましたが、これは江戸時代に広まった言い伝え。
- 由来には諸説あり、「駿河の名物(富士山、鷹、初物の茄子)」という説や、「徳川家康の好きなもの」とする説があります。
② 夢見占い
- 夢の内容によって吉凶を占う風習がありました。
- 例えば、「蛇の夢」は財運、「死人が出てくる夢」は吉兆、「歯が抜ける夢」は不吉など、多くの解釈が存在。
- 専門の「夢占い師」もおり、庶民の間で流行しました。
2. 夢と神仏の関係
江戸時代は、仏教や神道の影響が強く、「夢を通じて神仏のお告げを受ける」という考えが根付いていました。
① 淡島さまの夢占い
- 「夢の酒」に登場する淡島さまは、和歌山県の淡嶋神社(現・加太淡嶋神社)を中心に信仰されていた神様。
- 医療や安産、縁結びの神として信仰されるほか、「夢見の神」としても知られていました。
- 「淡島さまの上の句」を唱えて寝ると、自分が知りたいことが夢に現れるとされ、「夢占いの神」としても信じられていました。
② 夢告(むこく)
- 寺社では「夢の中で神仏からお告げを受けた」という話がよく語られました。
- 夢告を受けた人物が新しい神仏の信仰を広めたり、新しい寺社の建立を進めたりすることもあった。
- 例えば、京都の清水寺は「夢の中でお告げを受けた僧が滝を見つけたこと」から始まったと言われています。
③ 夢を叶えるための参詣
- 夢の中に「ある神社の名前が出てきた」場合、それはその神社に参拝せよという神の啓示と考えられました。
- 夢のお告げを信じた人々が、全国の神社仏閣にお参りすることもありました。
3. 夢を操作する方法? 江戸時代の「夢の続き」を見る習慣
「夢の酒」では、大旦那が夢の続きを見るために無理やり寝かされますが、実際に江戸時代には「夢の続きを見る方法」がいくつか伝えられていました。
① 夢の続きを見るためのおまじない
- 「枕を逆さにする」
→ 「夢の続きが見たい」と思ったら、枕の向きを変えて寝ると続きが見られると信じられていた。 - 「夢の内容を紙に書く」
→ 目が覚めたらすぐに夢の内容を紙に書くと、再び同じ夢を見やすくなると言われた。 - 「淡島さまの句を唱える」
→ 夢を操る方法の一つとして、夢占いの神に祈るという手法もあった。
② 「夢見の床」
- 特定の寝床や枕を使うと良い夢が見られると信じられていた。
- 例えば、旅先で神聖な場所(神社や寺の近く)で寝ると「良い夢を見られる」と言われた。
- 武士や商人の間では、何か大事な決断をするときに「夢見の床で寝てお告げを得る」という習慣もあった。
夢の酒を聞くなら「桂文楽」
桂文楽の「夢の酒」は、幻想的な物語と深い人情味が心に残る一席です。夢の話でありながら、お花の嫉妬心が笑いを誘うユニークな展開が魅力です。文楽独特の語り口で、夢と現実が交錯する世界を鮮やかに描き出します。
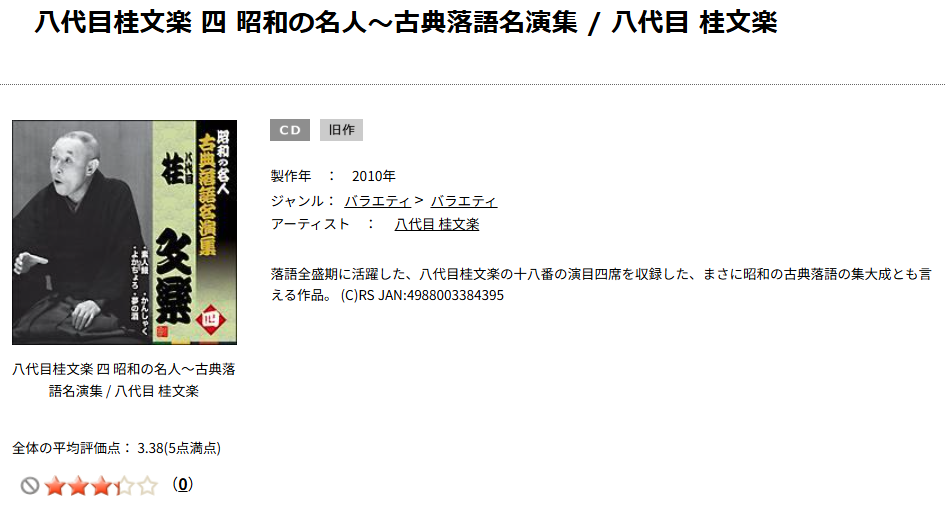
画像引用:TSUTAYA DISCASより

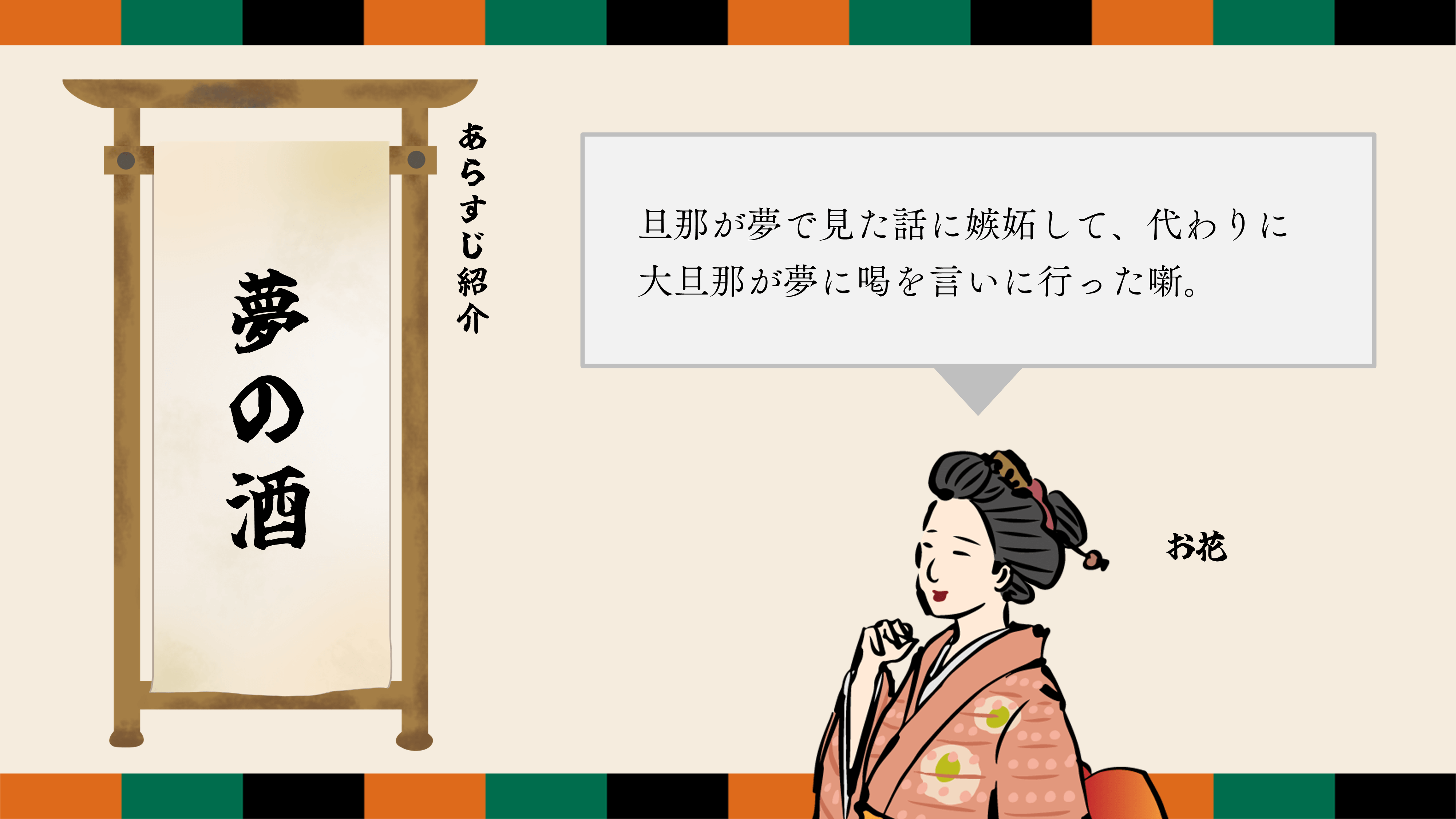



コメント