一言で「まんじゅう怖い」を解説すると…

暇つぶしに自分の怖いものの話をしていると、「まんじゅうが怖い」という奴が現れる噺。
主な登場人物

暇つぶしに自分の怖いものの話をしようと持ち掛けた男です!

ヘビが怖いヤスです!
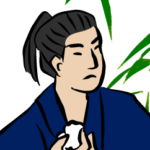
怖いものはないテツさんです!(まんじゅうが怖い・・・)
まんじゅう怖いの詳細なあらすじ
長屋に集まった若者たちが、暇を持て余して「何が怖いか」という話題で盛り上がっていた。
幽霊やクモ、ヘビやコウモリなど、さまざまな恐怖の対象が飛び交う中、一人の男だけが「俺には怖いものなんてない」と強がる。
しかし、周りからしつこく問い詰められると、彼はしぶしぶ「実はまんじゅうが怖い」と告白する。「まんじゅうの話をしているだけで気分が悪くなった」と言って隣の部屋に引っ込んでしまう。
残された若者たちは「あいつをまんじゅうで驚かせてやろう」とたくらみ、金を出し合って山ほどのまんじゅうを買い、彼の寝ている部屋にそっと運び込む。
男が目を覚ますと、部屋いっぱいのまんじゅうに驚いたふりをしつつ、「こんなに怖いものは食べてしまわないと」と言って、次々とまんじゅうを平らげていく。
その様子を覗いていた若者たちは、彼が実はまんじゅう好きで、からかわれていたことに気づく。
怒った若者たちが「本当に怖いものは何だ!」と問い詰めると、
「今度は濃いお茶が怖い・・・」。
まんじゅう怖いを聞くなら
まんじゅう怖いを聞くなら「古今亭志ん生」
志ん生の特徴の一つは、その飄々とした話し方で、聞き手を自然に引き込む力である。「まんじゅう怖い」でも、志ん生の落語はあまり力まず、まるで日常の一コマを語っているかのような、リラックスした雰囲気が漂う。これが、若者たちの間で繰り広げられる何気ない会話や、まんじゅうを怖がると見せかけた男のずる賢さを、よりリアルに感じさせる。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。
1. 饅頭の起源と日本への伝来

● 饅頭はいつ、どこから日本に伝わったのか?
饅頭は中国が発祥で、諸説ありますが、日本には鎌倉時代から室町時代にかけて伝わったとされています。特に以下の二つの説が有力です。
- 1241年(仁治二年):聖一国師が宋から持ち帰る
- 宋から帰国した禅僧・聖一国師(しょういちこくし) が、福岡の茶店に酒饅頭(酒麹を使った発酵饅頭)の製法を教えた。
- 1349年(貞和五年):林浄因が日本に饅頭を伝える
- 中国・元から来日した林浄因(りんじょういん) が、京都の建仁寺にて饅頭の製法を伝える。
- 彼は日本で初めての饅頭専門店「紅屋」を開き、そこから和菓子文化が広がった。
➡ 林浄因の系統が、現在の「日本の饅頭文化」の元になったとされる。
● なぜ饅頭は「小豆あん入り」になったのか?
もともと中国の饅頭は「肉まん」に近いものでした。しかし、仏教の影響で僧侶が肉を避けたため、代わりに小豆を使った餡(あん)を詰めるようになったと言われています。
- 中国の饅頭 → 肉入り、野菜入り
- 日本の饅頭 → 小豆餡入り
この変化が、日本独自の和菓子文化を生み出しました。
2. 江戸時代のまんじゅう文化

参照:全国和菓子協会より
● 江戸時代のまんじゅうの種類
江戸時代になると、庶民の間でもまんじゅうが普及し、多様な種類が生まれました。
- 酒饅頭(さかまんじゅう)
- 室町時代末期に誕生し、江戸時代に一般化。
- 甘酒を使って発酵させた皮が特徴 で、ほんのり甘く、モチモチした食感がある。
- 蒸し饅頭(むしまんじゅう)
- 現在の温泉まんじゅう に近い。
- 皮はしっとりしており、主にあんこ入り。
- 各地の温泉地で名物化される。
- 焼き饅頭(やきまんじゅう)
- 皮を香ばしく焼き上げたもの。
- 上州(群馬)などで特に人気があり、現代の「群馬焼きまんじゅう」の原型。
- 葛饅頭(くずまんじゅう)
- 夏の涼菓として人気。
- くず粉を使用し、ぷるぷるした食感。
- 栗饅頭(くりまんじゅう)
- 皮に卵を塗って焼いた、黄金色の外見が特徴。
- 蕎麦饅頭(そばまんじゅう)
- 蕎麦粉を使った生地で作られる。
- そば文化の盛んな江戸で人気。
➡ 江戸時代はまんじゅうの黄金期!将軍や大名がまんじゅうを好んだことで、各地の名物まんじゅうが生まれた。
3. 江戸時代のまんじゅうの価格は?
江戸時代の物価は現代と異なりますが、まんじゅうの価格は庶民にとっては比較的手頃なものでした。
- 白あん入り茶巾饅頭 → 5文(現代の500円前後)
- つぶあん入り小倉饅頭 → 2文(現代の200円前後)
➡ 「まんじゅう怖い」の話の背景として、庶民が気軽に買える和菓子だったことが分かる。
まんじゅう怖いを聞くなら「古今亭志ん生」
志ん生の特徴の一つは、その飄々とした話し方で、聞き手を自然に引き込む力である。「まんじゅう怖い」でも、志ん生の落語はあまり力まず、まるで日常の一コマを語っているかのような、リラックスした雰囲気が漂う。これが、若者たちの間で繰り広げられる何気ない会話や、まんじゅうを怖がると見せかけた男のずる賢さを、よりリアルに感じさせる。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。

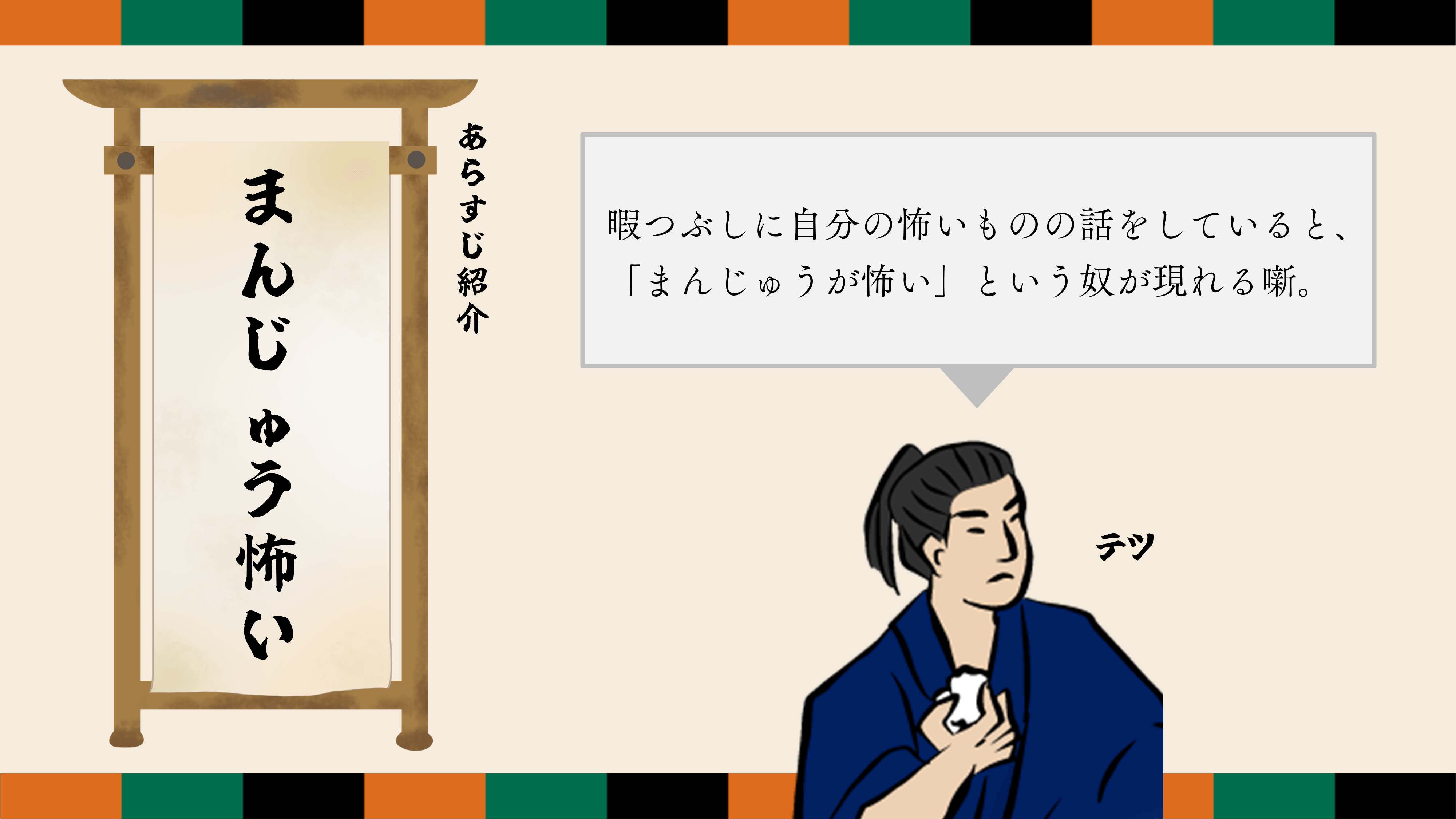




コメント