一言で「三方一両損」を解説すると…

三両の入った財布を落とし、拾った男と喧嘩し、最終的に奉行所で丸く収まる噺。
主な登場人物

三両の入った財布を拾った金太郎です!
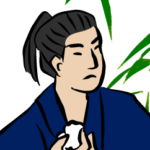
財布を落とした大工の吉五郎です

吉五郎の長屋の大家です

金太郎の長屋の大家です

この度の件を取り扱う大岡越前守だ!
三方一両損の詳細なあらすじ
神田白壁町に住む左官の金太郎は、柳原で書付けと印形、そして三両が入った財布を拾い、面倒に思いながらも、書付けにあった神田竪大工町の大工、吉五郎に届けに行くことにした。
吉五郎の家に着くと、吉五郎は鰯の塩焼きで一杯やっていた。金太郎が財布を差し出すと、吉五郎は書付けと印形は大事だから受け取るが、金はもう自分のものではないので受け取れないと主張する。
二人は「受け取れ」「受け取れない」の言い合いを始め、ついには取っ組み合いの喧嘩になる。騒ぎを聞いた隣人が大家を呼びに行き、大家が駆けつける。
大家は、吉五郎に対して「親切に届けてくれたものを素直に受け取り、後で礼をするのが人の道だ」と叱るが、吉五郎は強情に「そんなことを言われる筋合いはない」と反発する。
呆れた大家は、南町奉行の大岡越前守に訴えると宣言し、金太郎を引き上げさせる。
金太郎が自分の長屋の大家にこの件を話すと、「それではこちらの面子が立たない。先手を打ってこちらから訴えよう」と言い、願書を持って南町奉行所へ行くことに。
二人は奉行所に呼び出され、大岡越前守の調べが始まる。
大岡越前守は、事の顛末を聞き、「それならば三両は預かろう。そして、二人とも正直に行動したことに対する褒美として、それぞれに二両ずつ与えよう」と提案する。
これにより、三方とも一両ずつ損をした「三方一両損」という裁定が下される。金太郎も吉五郎もこれをありがたく受け入れ、全員が納得する。
その後、奉行所ではご馳走が振る舞われ、鯛の塩焼きに真っ白な炊き立てのご飯が出される。金太郎と吉五郎は、そのご馳走に舌鼓を打ちながら、腹が減ったらまた喧嘩をして奉行所に来ようなどと調子の良いことを言い始める。
大岡越前守「両人とも、いくら空腹だからといって、そんなにたくさん食べるなよ」
吉五郎「多かあ(大岡)食わねえ」
金太郎「たった一膳(越前)」
三方一両損を聞くなら
三方一両損を聞くなら「三笑亭 可楽」
低い声で舌足らずな話し方が特徴な三笑亭可楽。長尺になりがちな人情噺でも短く切り上げ、芸風は地味なものの聞くうちにハマりコアなファンがつく玄人芸。三方一両損も13分で聞けます。
\Amazon Audileで聞けます/
名奉行・大岡越前守の代表的な裁き

大岡越前守(大岡忠相)は、江戸幕府の南町奉行として数々の名裁きを残しました。その裁きは「大岡裁き」として語り継がれ、庶民の信頼を集めました。以下に、代表的な逸話を詳しく紹介します。
1. 白子屋事件(しらこやじけん)
《概要》
白子屋という質屋の娘が、ある日突然何者かに殺害されました。白子屋の主人は町奉行所に訴え出ますが、犯人の手がかりがまったくなく、事件は迷宮入りしそうになります。
《大岡越前守の裁き》
犯人は娘の奉公人ではないかと疑われたものの、決定的な証拠がありませんでした。そこで、大岡忠相は容疑者を呼び出し、「事件の再調査を行うので、犯行当時の詳しい状況を説明せよ」と詰め寄ります。
犯人は動揺し、取り調べの途中でつい「殺すつもりではなかった」と漏らしてしまいました。この一言が決定的証拠となり、犯人は自白。こうして事件は無事解決しました。
《ポイント》
当時の捜査は現代のような科学捜査ではなく、奉行の知恵と心理戦が頼りでした。大岡忠相の「巧みな尋問術」によって、真相が明らかになったのです。
2. 縛られ地蔵(しばられじぞう)
《概要》
ある商人が、「お堂の賽銭箱が盗まれた」と奉行所に訴え出ました。しかし、目撃者はおらず、事件は難航します。そんな折、ある男が「地蔵が賽銭を盗んだ」と嘘をついて、うまくごまかそうとしました。
《大岡越前守の裁き》
大岡忠相は、「それならば、その地蔵を縄で縛って連れてこい」と命じました。すると、町の人々が驚き、その男も動揺して「そんなことをしても無駄だ」と叫びました。
大岡忠相は、「では、お前は地蔵が賽銭を盗めないことを知っていたのか? なぜ知っている?」と問い詰め、男はとうとう自分が賽銭を盗んだことを自白しました。
《ポイント》
この裁きは、単なる法の執行ではなく、「犯人の心理を巧みに利用した名推理」の一例です。
3. 盗まれた財布と落とし主の嘘
《概要》
ある日、一人の町人が奉行所にやってきて、「財布を拾ったのですが、落とし主が名乗り出てきて困っています」と訴えました。
その財布には、大金が入っていたため、名乗り出た落とし主が「自分の財布だ」と強く主張していたのですが、実際にその人物が本当の落とし主なのかどうかが不明でした。
《大岡越前守の裁き》
大岡忠相は、落とし主の男に「では、お前の財布の中には何が入っていたか?」と尋ねました。男は「金が入っていた」と即答しましたが、細かい金額や中身の詳細をうまく説明できませんでした。
そこで大岡忠相は「ならば、一度財布の中を確認しよう」と言い、財布を開けさせました。すると、財布の中には小さな紙が一枚入っており、そこには「財布を拾った方は奉行所までお届けください」と書かれていました。
本当の落とし主ならば、この紙の存在を知っているはず。しかし、男はその紙についてまったく言及しなかったため、「この男は嘘をついている」と判明し、訴えは退けられました。
《ポイント》
この裁きは、落とし物の処理に関する現代の考え方にも通じる話で、「証拠の確保」と「証言の矛盾」を突く鋭い推理が光る一件です。
2. 南町奉行所とは?

画像参照:東京トリップより
江戸時代の町奉行所は「南町奉行所」と「北町奉行所」の2つに分かれており、交代で行政・司法を担当しました。
- 南町奉行所
- 大岡越前守が務めた奉行所で、現在の日本橋・京橋・芝などの南部地域を管轄。
- 民事・刑事事件の裁判、治安維持、市場や商取引の監督などを担当。
- 町民からの訴えを受け付け、庶民のトラブル解決にも関与した。
- 北町奉行所
- 江戸の北側(上野・浅草など)を管轄。
- 南町奉行所と同じ役割を持ち、交代で業務を担当。
奉行所には、与力や同心といった役人が働いており、大岡忠相はこれらの人々を統率しながら江戸の治安を守っていました。
3. 江戸時代の落とし物に対する感覚
現代と同じく、江戸時代にも落とし物に関するルールが存在しました。当時の人々は、落とし物に対してどう接していたのでしょうか?
江戸時代の遺失物ルール
- 拾ったお金はどうする?
- 原則として、拾った金銭は半分を拾い主が受け取ることができた。
- ただし、反物(布地)などの品物は持ち主に返却するのが基本。
- 落とし物はどこに届ける?
- 落とし主が判明していれば、大家や長屋の年寄(管理者)を通じて届ける。
- 届け先がない場合は町奉行所に届けられ、半年間保管された。
- 落とし物が見つからない場合
- 半年経過しても持ち主が現れなければ、拾い主の所有物になるというルールがあった。
- 道徳的な考え
- 落とし物を届けることは「正直者の美徳」とされ、拾得者が堂々と届けることが多かった。
- 『三方一両損』でも、左官の金太郎が大工の吉五郎に財布を返そうとする姿勢は、江戸時代の道徳観を反映している。

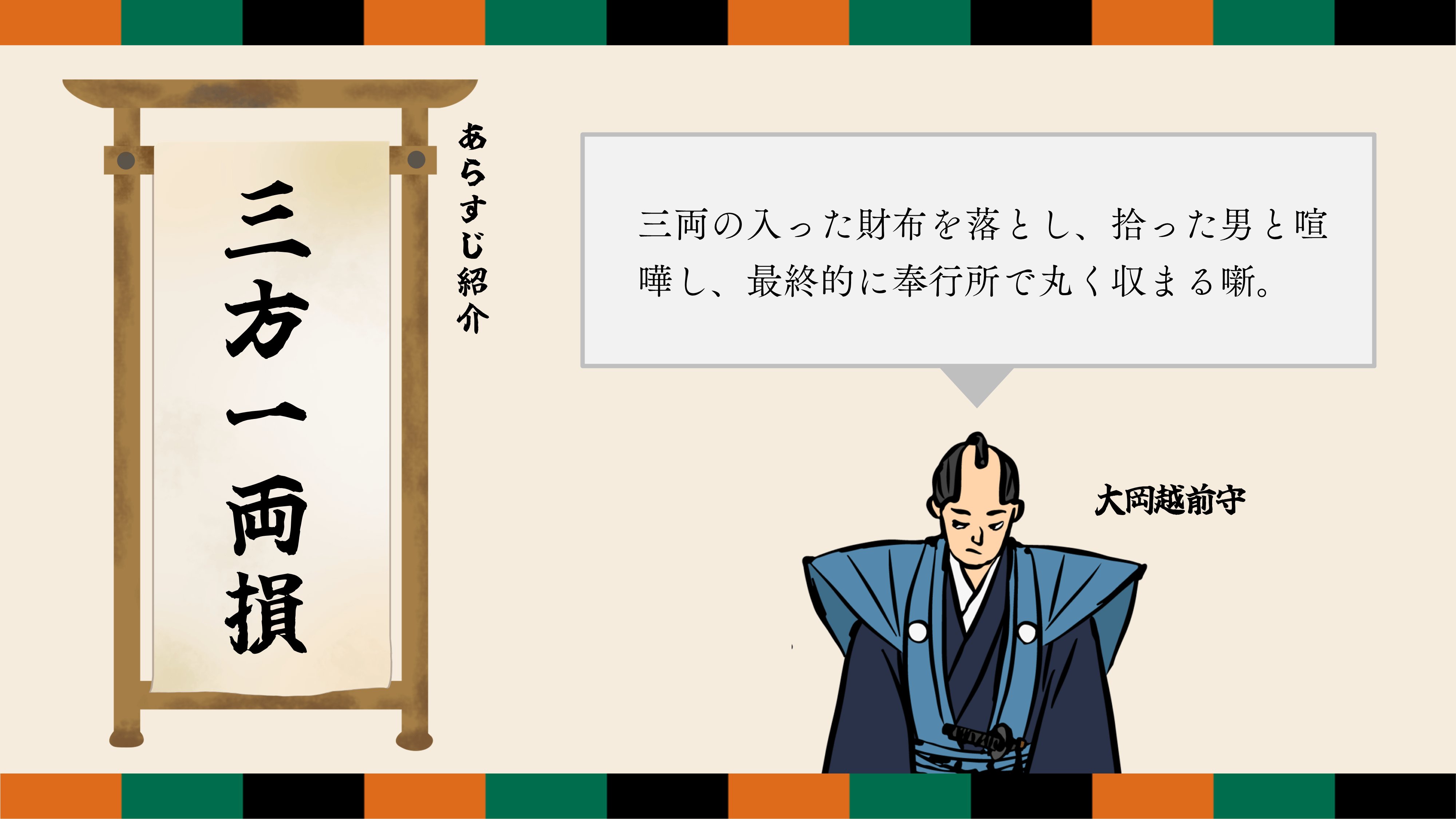




コメント