一言で「うどん屋」を解説すると…

うどんを頼まない酔っ払いに絡まれ、期待通りに注文が取れないうどん屋の噺。
主な登場人物

鍋焼きうどんを売ってます・・・

うどん屋に絡んだ酔っ払いだぁ!

うどんを頼んだ奉公人です・・・
うどん屋の詳細なあらすじ
屋台でうどんを売るうどん屋に、酔っ払いがふらふらと近づいてくる。酔っ払いは屋台の前で立ち止まり、火に当たりながら絡んでくる。
酔っ払いは「うどん屋、お前、仕立屋の太平を知ってるか?あの太平の一人娘、ミー坊が結婚したんだよ。その婚礼の帰り道さ、ミー坊が俺の前にひれ伏して、『おじさん、今回はいろいろお世話になりました』なんて言うんだぜ。あの、ちょっと前まで鼻垂らしてたミー坊がさ、どう思うよ、うどん屋?」
と、何度も同じ話を繰り返し、うどん屋に相槌を打たせる。酔っ払いはさんざん喋った挙句、うどんを頼まずに行ってしまう。
うどん屋は気を取り直して「鍋焼き~うど~ん」と声を張り上げて屋台を引き始めるが、すぐに「ちょっと、うどん屋さん」と声がかかる。喜び勇んで振り返ると、「子どもが寝たばかりだから静かにしてちょうだい」と注意される始末。
今日はついてないと思いながら、表通りへ出ると、大きな店の前で若い衆から小さな声で「うどん屋さ~ん」と声がかかる。
奉公人が何十人もいるような大店で、今日はここで一儲けできると期待を膨らませるうどん屋。主人にばれるのを恐れて小さな声で話しかけたんだと考えれば合点がつく。
うどん屋も小声で「いくつだい?」と尋ねると、若い衆はささやき声で「一つ」と返答。少しがっかりするも、味見役の小僧だから旨ければ、あとで注文が入ると考え、熱々のうどんを差し出す。
若い衆は黙々とうどんを食べ、汁まで飲み干す。
若い衆が小さく「ごちそうさま、おいくらだ?」と尋ねると、うどん屋は感謝しながら代金を受け取る。しかし、若い衆がさらに、ささやき声で「うどん屋さ~ん」と呼びかけるので、追加注文かと身を乗り出し、こちらも「へぇ~い・・・」と小さな声で返事をしてやる。
若い衆「お前さんも風邪を引いたのかい?」。
うどん屋を聞くなら
うどん屋を聞くなら「柳家小さん」
柳家小さんの「うどん屋」は、彼の柔らかく穏やかな語り口が、噺の温かさを引き出し、聴く者にほっとするような心地よさを与えてくれる一席である。小さんの語りの魅力が詰まった作品と言えるだろう。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから無料登録をしてご視聴頂けます。
江戸時代の「うどん屋」と「そば屋」の立ち位置の違い
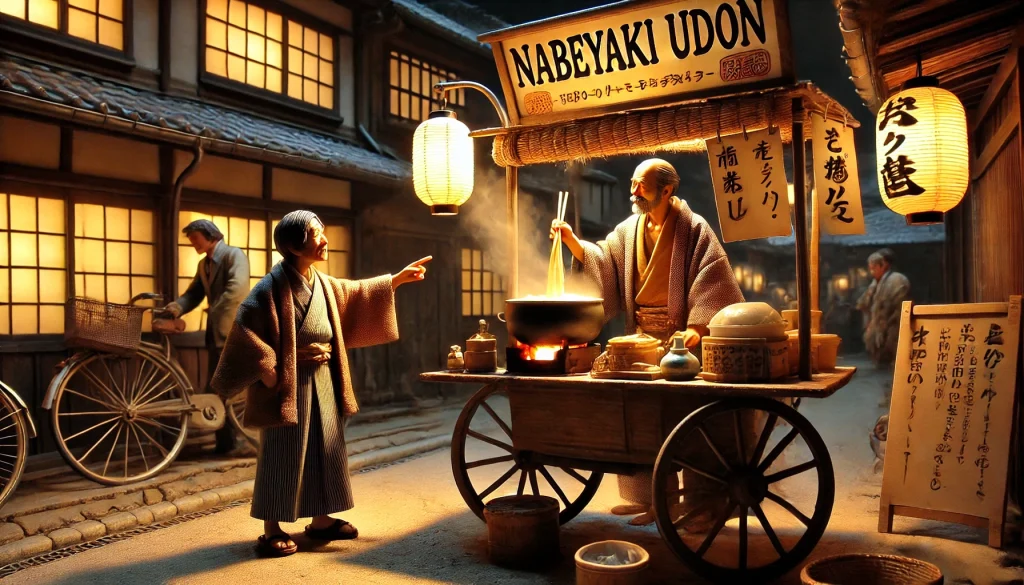
落語『うどん屋』をより深く理解するために、江戸時代における「うどん」と「そば」の違い を掘り下げると、当時の食文化や庶民の生活がよりリアルに見えてくる。
1. そば屋 vs. うどん屋:どちらが主流だったのか
江戸時代後期、そばの方が「江戸のファストフード」として圧倒的に人気だった。
- 「そば」と「うどん」の消費比率 → 江戸は圧倒的にそば文化
- 関東(江戸) → そばが主流
- 関西(上方) → うどんが主流
- 江戸の庶民は「そば派」が圧倒的多数 で、うどん屋は「少数派」の立場だった。
- そば屋は店舗型も多く、屋台も活発 に営業していた。
- そばが人気だった理由
- ① 江戸の水は硬水で、そばの方がうどんより美味しく茹でられた。
- ② そば粉の価格が下がり、庶民でも気軽に食べられるようになった。
- ③ 「短時間で提供できる」→ 効率の良い商売になった。
→ 結果として、そば屋は江戸の町に広く浸透し、屋台も多く出た。
2. うどん屋の立ち位置
「江戸はそば文化」と言われるが、うどん屋がまったく存在しなかったわけではない。
むしろ、うどん屋は「夜食」としての立ち位置が強かった。
- そば屋は「昼向き」、うどん屋は「夜向き」
- そば屋 → 昼間の食事として利用されることが多い。
- うどん屋 → 夜食・深夜の屋台として営業することが多い。
- なぜうどん屋は「夜食」向きだったのか?
- ① 消化がよく、胃に優しい → 夜に食べても負担が少ない。
- ② 飲んだ後の「締めの一杯」として最適 → 酒飲みが多い江戸では、夜の需要があった。
- ③ 汁が温かく、体が冷えた時にちょうどいい → 屋台で寒い夜に食べるのにぴったり。
→ 『うどん屋』の舞台設定が「夜の屋台」であるのは、まさに当時の文化に即したリアルな描写だった。
3. そば屋とうどん屋の「価格」の違い
- そばの方が若干高級なイメージ
- そば粉は、当初は高価だったが、江戸時代後期には安定供給されて庶民にも広まった。
- ただし、そば屋の店舗は「ちょっと贅沢」な外食の場所として機能していた。
- 「そば切り」(現在のざるそばに近いもの)など、高級な食べ方もあった。
- うどんは、より庶民的な食べ物
- そばよりも小麦粉を主原料とするため、うどんは比較的安価に提供されていた。
- そのため、屋台で気軽に食べられる「夜食」としての役割が強かった。
→ そば屋は「江戸のグルメ」、うどん屋は「庶民の夜食」という住み分けがあった。
4. そば屋 vs. うどん屋:落語における扱いの違い
落語では、そば屋・うどん屋のどちらも登場するが、扱われ方には微妙な違いがある。
- そば屋が登場する噺
- 『時そば』
- そば屋が「粋」な江戸っ子の食べ物として登場。
- そばの値段をごまかす男の話 → 「江戸の庶民の知恵と機転」がテーマ。
- 『そば清』
- 大食い自慢の男がそばを食べ過ぎる話。
- 『時そば』
- うどん屋が登場する噺
- 『うどん屋』(今回の話)
- 酔っ払いとのやりとりや、屋台の商売の難しさが描かれる。
- 『時うどん』(関西版『時そば』)
- 『時そば』の関西版として、「そば」ではなく「うどん」が題材になっている。
- 関東=そば文化、関西=うどん文化 の違いを反映している。
- 『うどん屋』(今回の話)
→ 落語において「そば」は粋な食べ物、「うどん」は庶民の夜食・寒い日の温かい食事として描かれることが多い。
5. 現代における「そば vs. うどん」
江戸時代の「そば文化 vs. うどん文化」の構造は、現在も少し残っている。
- 関東では「そば派」が多く、関西では「うどん派」が多い。
- これは、水質や出汁文化の違いに起因している。
- 関東は「醤油ベースの濃いつゆ」、関西は「昆布だしベースの薄いつゆ」。
- 「そばは江戸っ子の粋」「うどんは関西の庶民の味」といったイメージが今でも残る。
→ 『うどん屋』という落語は、今でいう「深夜のラーメン屋」のような立ち位置。
→ そば屋と比べて、より「庶民的で気軽な存在」として描かれているのが面白い。
うどん屋を聞くなら「柳家小さん」
柳家小さんの「うどん屋」は、彼の柔らかく穏やかな語り口が、噺の温かさを引き出し、聴く者にほっとするような心地よさを与えてくれる一席である。小さんの語りの魅力が詰まった作品と言えるだろう。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。

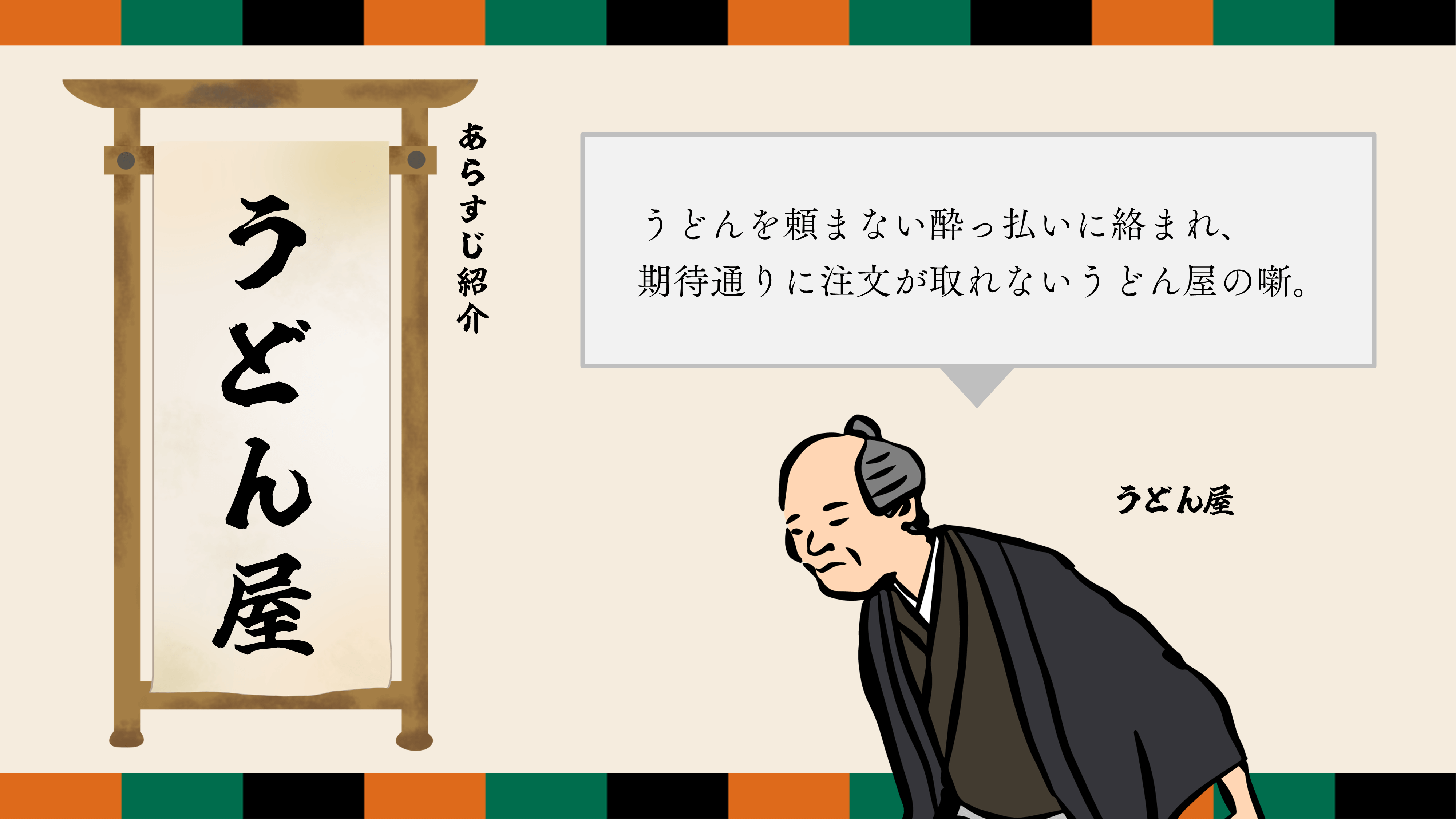




コメント