一言で「禁酒番屋」を解説すると…

禁酒の御触れが出された城に酒を届けるために悪戦苦闘する噺。
主な登場人物

城に酒を持ってこさせるように依頼した武士じゃ!

近藤に依頼を受けた酒屋の番頭です!

酒屋の手代の者です!

禁酒の番を務めている役人だぁ!
禁酒番屋の詳細なあらすじ
ある藩で若侍同士が花見の宴で口論となり、酒の勢いで真剣勝負になってしまい、一方が斬られて死に、もう一方も切腹してしまった。
これを受けて、殿様は藩内で禁酒を命じたが、酒好きの武士たちは酒をやめられず、酔ったまま城に戻るようになる。藩は城内への酒の持ち込みを防ぐため、検問所「禁酒番屋」を設ける。
酒好きの近藤という武士が、酒屋に一升酒を届けるように頼むが、酒屋は困り、カステラの箱に酒を隠して城に持ち込もうとする。しかし、門番に見破られ、「この偽りものめが!」と言われ、酒は飲まれてしまう。
次に、油屋を装って酒を持ち込むが、これも失敗し「この偽りものめが!」と言われてこの酒も飲まれてしまう。
最後に、酒屋の若い者は小便を徳利に入れて「小便を持ってきた」と言って門番を騙そうとする。門番は徳利の中身を調べようとし、酒だと思い、飲んでようやく気づき、「けしからん」と叱る。
若い者「はじめから小便だとおことわりしていました!」
門番「う~ん、この正直者めが・・・」
禁酒番屋を聞くなら
禁酒番屋を聞くなら「林家たい平」
林家たい平の「禁酒番屋」は、酒にまつわる騒動をユーモラスに描いた一席です。禁酒令に翻弄される酒屋と番屋の姿を、たい平の軽妙な語りで楽しめます。笑いと風刺が絶妙に絡み合う、痛快な作品です。
\Amazon Audileで聞けます/
1. 江戸時代の禁酒令とは?

江戸時代には、藩や幕府が禁酒令を発令することがあった。これは以下のような理由によるものだった。
- 治安維持のため
武士同士の争い、町人や農民の暴動を防ぐため、酒席での喧嘩や刃傷沙汰を抑えようとした。- 実例:会津藩(現・福島県)の藩主・保科正之は、藩内の乱れを防ぐために酒を制限したと言われる。
- 『禁酒番屋』の背景:落語の中では、藩の武士が花見で酒を飲みすぎた結果、真剣勝負に発展し、藩主が全面禁酒を命じることになる。
- 倹約政策の一環として
酒は贅沢品とみなされ、消費を抑えるために禁酒令が出されることもあった。特に大飢饉の際などには、穀物の利用を食糧優先とするために酒造を制限することもあった。- 実例:享保の改革(1716~1745年)では、幕府が「質素倹約」を奨励し、酒造の取り締まりを強化した。
- 健康・風紀の乱れを防ぐため
酒は士農工商問わず広く飲まれていたが、特に武士が酒に溺れて職務を怠ることは問題視されていた。そのため、規律を守るために禁酒令が出されることもあった。
2. 禁酒令に対する庶民と武士の反応
禁酒令が出されても、人々は簡単には酒を手放さなかった。
- 隠れて飲む手口
幕府や藩が取り締まっても、庶民や武士たちはさまざまな手法で酒を飲み続けた。- 油壺やカステラ箱に隠す(落語『禁酒番屋』の例)
- 湯漬け(酒をお茶に混ぜる)
「酒ではなく湯漬けだ」と偽って飲む手法。 - 「薬」と称して飲む
「これは酒ではなく、養生酒(薬用酒)である」と言い張る。
- 幕府の対応
- 幕府や藩は、違反者に罰金や罰則を与えたが、大衆の抵抗も根強く、徹底的な取り締まりは困難だった。
- 結果として、禁酒令は形骸化することが多かった。
3. 江戸時代の酒文化
そもそも、江戸時代の人々にとって酒とはどのような存在だったのか?
① 酒は「庶民の娯楽」
- 居酒屋や屋台で手軽に飲めるようになり、労働者の楽しみとして広がった。
- 江戸では「宵越しの銭は持たぬ」と言われるように、日銭を稼ぐ町人が気軽に酒を飲み、明日のことは考えない風潮があった。
② 武士にとっての酒
- 武士の間では、「一気飲み」や「酒に強いこと」が美徳とされる傾向があった。
- 一方で、幕府は「武士たるもの、酒で取り乱すべきではない」との考えから、過度な飲酒を戒めることもあった。
③ 酒の種類と飲み方
- 熱燗:庶民の間では、お燗をつけて飲むことが一般的だった。
- 濁酒(どぶろく):米を発酵させた濁り酒で、農民や庶民の間でよく飲まれていた。
- 清酒(せいしゅ):現在のような透明な日本酒が登場したのは江戸時代後期であり、それ以前は濁り酒が主流だった。

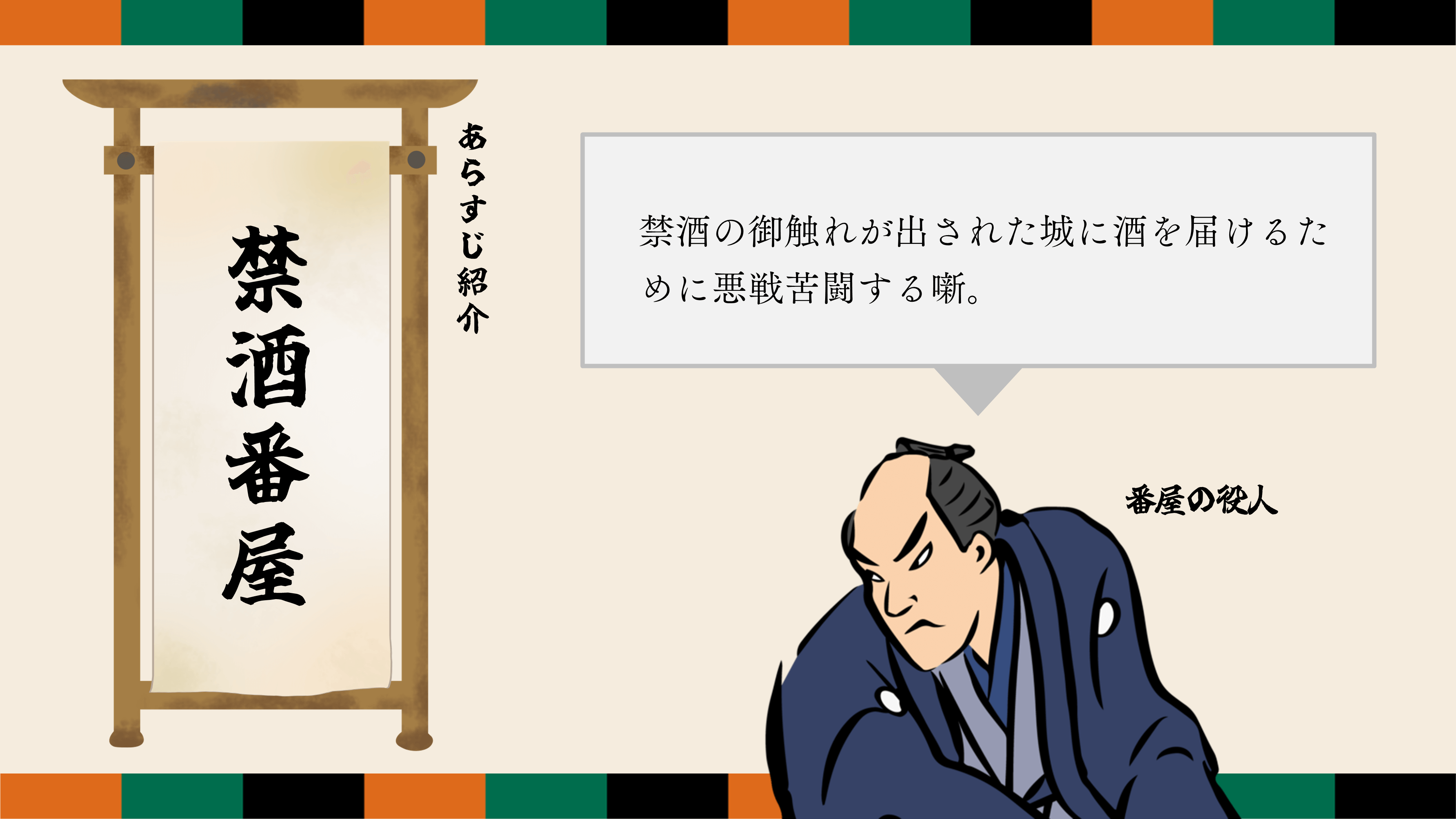




コメント