一言で「短命」を解説すると…

美人で働き者の妻がいるのに早死する亭主の理由を聞いて、自分が長生きなことを自覚する噺。
主な登場人物

美人の女房の旦那が立て続けに早死する噂を聞いた与太郎です

与太郎から早死する理由を聞かれた旦那です

与太郎の女房です
短命の詳細なあらすじ
植木職人の八五郎が、伊勢屋の一人娘の婿養子が立て続けに3人も亡くなった理由を知りたくて、横町の隠居を訪ねる。
隠居は、伊勢屋の夫婦仲が非常に良いことが原因だと推測する。隠居によれば、夫婦がいつも一緒にいて、美味しく栄養満点の食事を共にし、奥さんが美人で自分が暇になるという状況は、男性にとって短命の原因になるのだという。
八五郎が長屋に戻ると、相撲取りのような妻が八五郎を怒鳴りつける。隠居の話を思い出した八五郎は、妻にご飯を手渡してもらおうとするが、妻の指に触れて、
「あぁ、俺は長生きだ」。
短命を聞くなら
短命を聞くなら「立川談志」
立川談志の「短命」は、風刺と皮肉が絶妙に織り込まれた一席です。人間の業や欲望を鋭く描きつつも、笑いを通じて深い洞察を与えます。談志の個性が光る、考えさせられる名作です。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。
1. 江戸時代の美人の特徴

画像参照:喜多川歌麿Wikipediaより
江戸時代の美の基準は、当時の文化や生活習慣と深く結びついていました。主な特徴は以下の通りです。
① 面長の顔立ち
江戸時代では、卵型の顔が理想とされ、特に面長の顔が上品とされました。逆に、丸顔や小顔はあまり好まれなかったようです。
② 引き締まった細い目(切れ長の目)
現代では大きな目が美人の特徴とされますが、江戸時代では細く切れ長の目が「涼しげ」で上品とされていました。浮世絵に描かれる女性も、ほとんどが細い目をしていることから、その美意識が伺えます。
③ お歯黒と引眉(ひきまゆ)
既婚女性は眉を剃り、歯を黒く染める「お歯黒」が一般的でした。お歯黒は、歯の保護や既婚の証として重要視され、これを施すことが「美しさ」の一部と考えられていました。現代の美意識とは大きく異なる点の一つです。
④ 色白でふくよかな体型
「色の白いは七難隠す」という言葉があるように、色白の肌は美しさの象徴でした。また、ふくよかな体型は、栄養状態の良さや富の象徴とされ、理想的な美人像とされました。
江戸時代は現代と違い、痩せすぎは貧しさや病弱を連想させるため、あまり好まれなかったのです。
⑤ 黒髪の艶やかさ
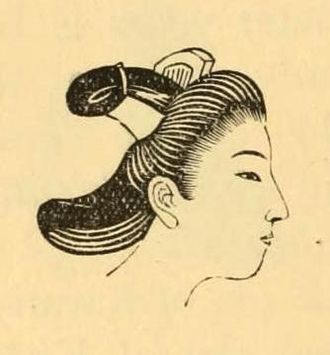
画像参照:島田髷Wikipediaより
髪は「女性の命」とされ、黒く艶やかな髪が美人の条件とされました。髪型にも流行があり、「島田髷(しまだまげ)」や「元禄島田」など、時代によってさまざまな結い方がありました。
2. 江戸時代の美人像が生まれた背景

これらの美の基準は、江戸時代の文化や社会的背景に根ざしています。
① 浮世絵の影響
江戸時代の美人画は、当時の美の基準を映し出しています。例えば、喜多川歌麿の「美人画」は、切れ長の目と面長の顔、白い肌が強調され、理想の女性像が反映されています。
② 身分や生活習慣の影響
武家や裕福な商人の妻は、日焼けを避け、白粉(おしろい)を使って色白を保ちました。労働をしない女性ほど色白でふくよかになりやすく、それが「上品さ」と結びついていきました。
③ 健康と富の象徴
ふくよかな体型は、食に恵まれた裕福な家の証でした。当時の庶民は質素な食生活だったため、ふくよかな女性は「恵まれた環境で育った美人」と見なされました。

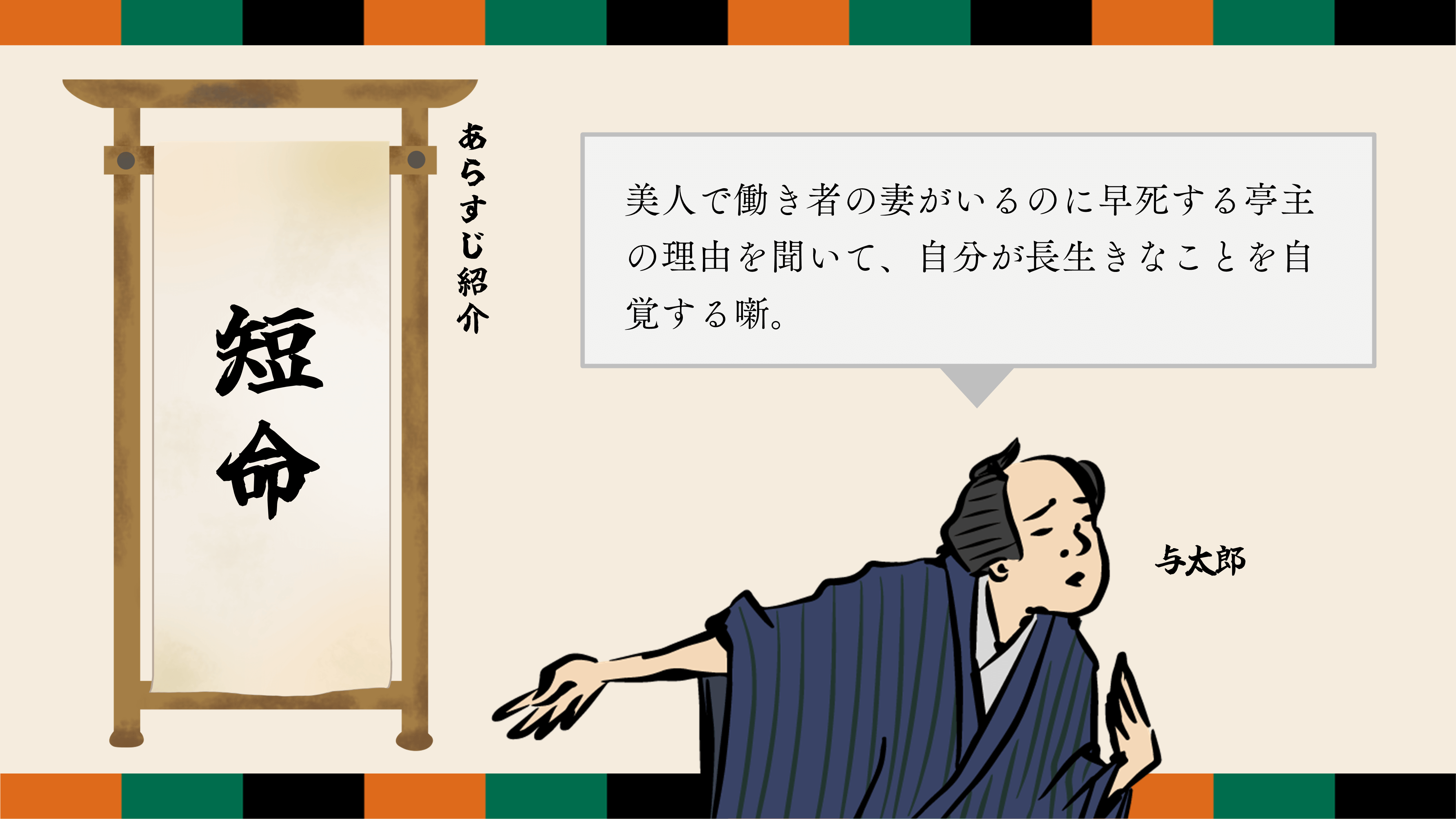




コメント