一言で「猫の皿」を解説すると…

茶屋で猫に高価な茶碗で飯を食わせていたのを見て、猫を買って茶碗をもらおうとした噺。
主な登場人物

茶屋で高価な高麗の梅鉢茶椀だと気づいた男です!

茶屋のじいさんです!
猫の皿の詳細なあらすじ
江戸の道具屋が田舎で掘り出し物を探していたが、大した収穫もなく江戸に戻る途中、茶店で休憩する。そこで、道具屋は猫が飯を食べている皿が高価な高麗の梅鉢茶椀だと気づく。
この茶椀を手に入れようと、猫好きを装って猫を抱き、茶店の爺さんから猫を3両で買い取る。さらに、猫に使い慣れた皿をくれと言って茶椀を手に入れようとするが、爺さんは「この茶椀は300両もするので手放せない」と断る。
計画が失敗した道具屋は、猫に引っ掻かれ、小便をされるなど散々な目に遭う。
道具屋「なぜ、そんな高価な茶椀で猫に飯を食わせるんだ?」
爺さん「この茶椀を使うと、猫がときどき3両で売れるんです」。
猫の皿を聞くなら
猫の皿を聞くなら「立川談志」
立川談志の「猫の皿」は、商人同士の駆け引きを描いた巧妙でユーモラスな一席です。高価な古い皿を巡る、したたかなやり取りが笑いを誘います。談志の鋭い語り口が、この滑稽話を一層際立たせる名作です。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。
1. 江戸時代の道具屋とは?

落語には「道具屋」が登場する噺がいくつかありますが、そもそも江戸時代の道具屋がどのような仕事をしていたのかを知ると、「猫の皿」の道具屋の行動がより納得できるものになります。
● 道具屋の役割
道具屋とは、古道具や骨董品、日用品などを仕入れて売る商売人 のことを指します。
現代でいうところの 骨董商やリサイクルショップのような存在 でした。
- 新しい道具ではなく、中古品や掘り出し物を扱う のが基本。
- 江戸の庶民は倹約志向が強かったため、新品よりも中古のほうが人気 だった。
- 古道具の価値を見極めて 「安く仕入れて高く売る」 ことが商売の基本。
→ 「目利き」ができることが、道具屋にとって最も重要なスキルだった。
● 道具屋の仕入れルート
道具屋が品物を仕入れる方法はいくつかありました。
- 江戸の町中での買取
- 家庭で不要になった家具や茶碗などを買い取る。
- 遺品整理や火事の後に売られる品なども狙い目だった。
- 田舎へ行って掘り出し物を探す
- 田舎では骨董品の価値を知らずに使っていることが多かった。
- 価値を知らない持ち主から安く買い、江戸で高値で売るのが狙い。
- 「猫の皿」の道具屋も、まさにこの手法を狙っていた。
- 寺社や大名屋敷の放出品
- 大名家や寺が財政難で品物を売ることがあり、それを買い取る。
- こうした品は本物の骨董品が多く、高額で売れた。
→ 道具屋の仕事は、単なる商売ではなく、「価値を見抜く目」が必要な職業だった。
● なぜ道具屋は茶店の皿に目をつけたのか?
- 田舎では高級品が「価値を知られずに使われている」ことがあると考えた。
- 猫に使わせるような皿なら、安く手に入るはずと油断した。
- しかし、実は爺さんのほうが一枚上手だった というオチが秀逸。
→ この背景を知ると、道具屋がなぜ皿を手に入れようとしたのかが、よりリアルに感じられる。
2. 高麗の梅鉢茶碗とは?

参照:五島美術館より
この噺の鍵となるのが、「猫が飯を食べていた皿が、実は高価な骨董品だった」という点です。
● 高麗の梅鉢茶碗とは?
「高麗の梅鉢茶碗」は、朝鮮半島で焼かれた高麗茶碗の一種 です。
高麗茶碗は、特に茶の湯(茶道)の世界で珍重され、江戸時代には非常に価値のある品でした。
- 「梅鉢」 とは、茶碗の内側に 梅の花のような模様があることから名付けられた。
- 侘び寂びを重んじる茶人たちに人気があり、数百両で取引されることもあった。
- 一見すると素朴な作りだが、茶の湯の世界では 「名物」として扱われる逸品だった。
→ つまり、茶店の爺さんは「ただの猫の餌皿」に見せかけて、実はとんでもないお宝を持っていた。
● 江戸時代における高麗茶碗の価値
江戸時代の茶道では、「唐物(中国の茶器)」が最も格上とされ、その次に「高麗茶碗(朝鮮の茶器)」が珍重されました。
- 高麗茶碗は、特に千利休の時代から 「素朴な美しさを持つ器」として評価が高かった。
- 侘び茶(わびちゃ)の精神に合う とされ、将軍や大名クラスの茶人が好んだ。
- 「名物」とされる茶碗の中には 数百両、場合によっては千両単位の値がつくものもあった。
→ 猫が食べていた皿が実は超高級品だった、というギャップが話の面白さになっている。

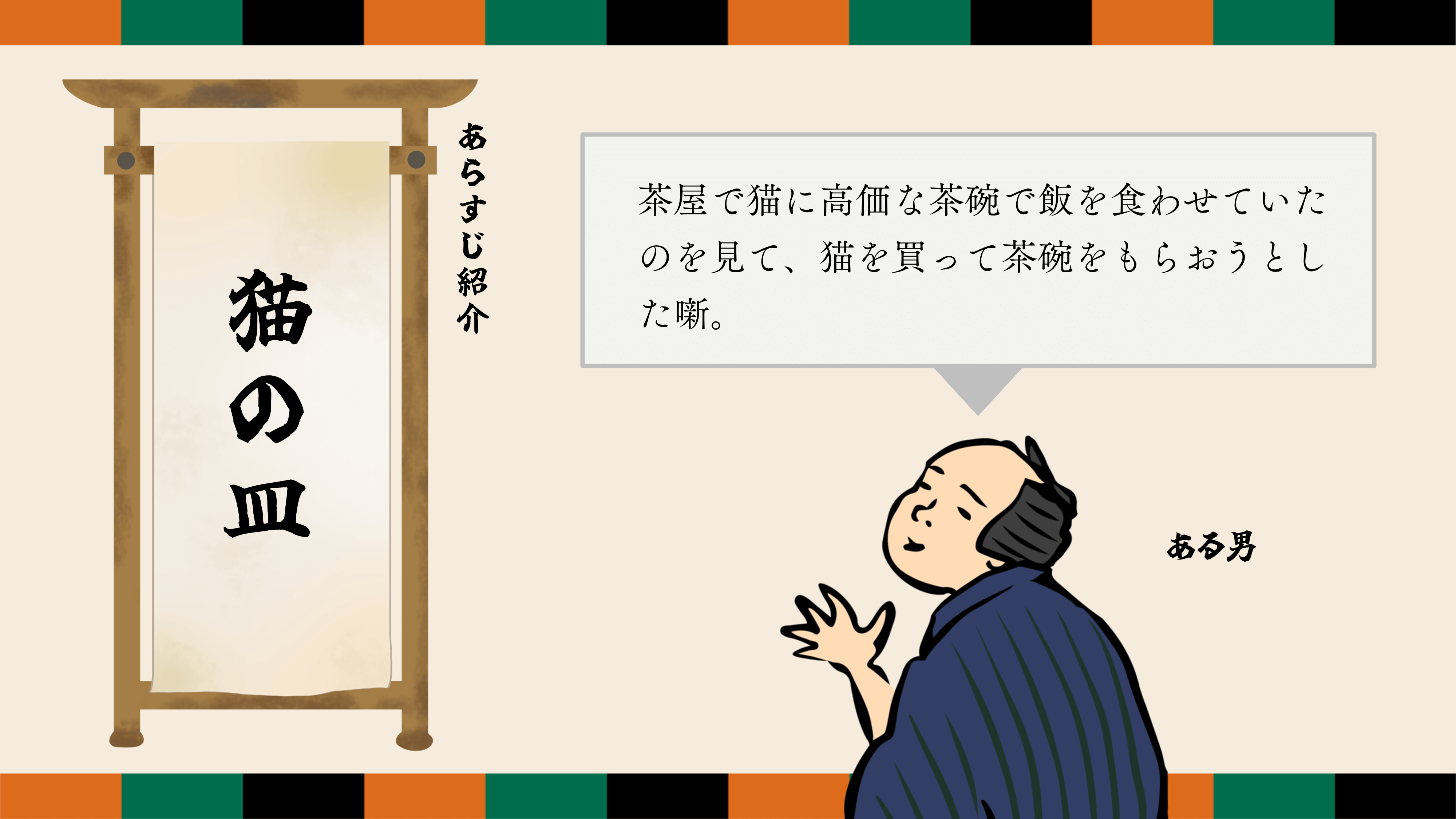




コメント