一言で「死神」を解説すると…

自殺しようとしたら死神が現れ、医者になって金を稼げと言われる噺。
主な登場人物

自殺しようとした男です・・・

旦那に愛想をつかした女房です・・・
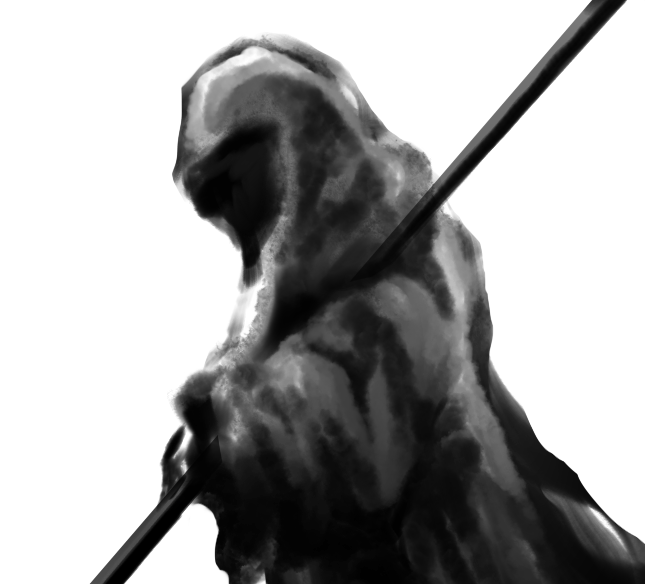
自殺しようとした男に医者になれと言った死神・・・
死神の詳細なあらすじ
男は家で金の工面ができず、女房から罵倒され、絶望のあまり首をくくろうと思って家を飛び出す。
大きな木の下で首をくくろうと考えていると、突然死神が現れる。死神は男に、「お前はまだ寿命があるから、死ぬことはできない。代わりに金を儲ける方法を教えてやろう」と言う。
死神の男に医者になれと言いだす。「医者になって、病人の寝ている場所で死神が足元に座っていれば、呪文を唱えてその病人は助かる。しかし、枕元に座っているなら、寿命が尽きているので助けることはできない」と。
男は半信半疑ながらも、医者としての看板を掲げてみると、すぐに依頼が舞い込む。最初の依頼は、日本橋の越前屋四郎兵衛の家の病人を診ることだった。
男が訪れてみると、病人の枕元には死神がいなかった。男は教わった呪文を唱え、手を打つと、死神は消え、病人は元気を取り戻す。
この出来事が評判となり、男はたちまち大繁盛し、莫大な利益を得る。男はその金で豪勢な暮らしを始め、古い家族と別れ、若い女と一緒に豪遊するようになる。
しかし、やがてその浪費がたたり、全ての金を使い果たし、若い女にも去られる。再び医者の仕事を始めるが、今度はどの家に行っても死神が枕元に座っており、助けられる病人がいなくなる。
そんな中、ある日、麹町の伊勢屋伝右衛門から依頼が来る。男が訪れると、またしても死神が枕元に座っていた。
伝右衛門から寿命を延ばすために大金を提示され、欲に目がくらんだ男は、死神の位置を無理やり足元に変える計略を思いつく。
男は若い衆を使って布団を半分回し、死神を足元に移動させて呪文を唱える。死神は驚き、計画は成功して、病人は命を取り戻す。
家に帰った男が酒を飲んでいると、死神が現れ、男を暗い洞窟へと誘う。そこには無数の蝋燭があり、それぞれが人間の寿命を表しているという。
死神は、男の蝋燭が今にも消えそうだと告げる。男は恐怖に駆られ、死神に助けを求める。
死神は、蝋燭をつなぎ合わせれば命が延びると言うが、男の手は震えて蝋燭をつなぐことができない。
そして、男の蝋燭はついに消え、男の命も尽きる。
死神「消えるよ消えるよ・・・ほ〜ら消えた・・・」
死神を聞くなら
死神を聞くなら「三遊亭圓生」
三遊亭圓生の落語「死神」は、独特なユーモアと緊張感が絶妙に交わる物語で、聞き手を最後まで引き込む名作です。人間の生死に対する鋭い洞察が光る一席。
1. 江戸時代の寿命観

『死神』における「ろうそく=寿命」の概念は、江戸時代の人々が持っていた死生観と密接に関わっている。
(1) 平均寿命と寿命の考え方
- 江戸時代の平均寿命は 30~40歳程度 だったとされるが、これは幼児死亡率が高かったための数値。
- 50~60歳まで生きる人も珍しくはなく、特に武士や商人の上層階級は比較的長寿だった。
- 「寿命は神仏によって決まる」 という考え方が強く、「運命」や「因果」として受け入れられていた。
(2) 「寿命が尽きる」とはどういうことか?
- 当時は「病気で死ぬ」のではなく、「寿命が尽きる」と考えられていた。
- 病名がはっきりしないことも多く、「寿命が来た」と思われることが多かった。
- これは『死神』の「ろうそくの火が消える=寿命が尽きる」という考え方に直結している。
→ 医療技術が未発達なため、実際には治療できる病気も、「もう助からない」と判断されるケースが多かった。
2. 江戸時代の医者とは?
『死神』では、主人公が「病人の寿命を延ばす方法」を学び、金儲けを企むが、実際の江戸時代の医者はどのような存在だったのか?
(1) 江戸時代の医者の種類
- 「漢方医(蘭方医)」
- 江戸時代の医療は主に 中国由来の漢方医学 が主流だった。
- 蘭学が広まるにつれ、西洋医学(蘭方医学)も一部で研究されるようになった。
- 「町医者」(庶民向け)
- 武士や裕福な商人には専属の医者がいたが、庶民は「町医者」に頼ることが多かった。
- 町医者の中には 無資格の「なんちゃって医者」 も多く、藪医者が横行。
- 「祈祷師・巫女」
- 正規の医者にかかるよりも、「神仏にすがる」ことの方が一般的だった。
- 実際、病気の原因がよくわからないため、「祟り」や「怨霊」のせいにすることが多かった。
3. 誰でも医者になれたのか?
- 江戸時代には 正式な医者になるための「医学校」 のようなものはなかった。
- ほとんどの医者は 師匠について学ぶ徒弟制度 で育った。
- 一部の有名な医師(例えば「杉田玄白」など)は、西洋医学を研究しながら独学で学んでいた。
- しかし、医療の知識を持たない 「なんちゃって医者」も多く、事実上、誰でも医者を名乗ることができた。
→ 『死神』の主人公が突然「治療法を教わっただけで医者になる」のは、当時の医療事情を考えると不自然ではない。
4. 江戸時代に「寿命を延ばす方法」はあったのか?
『死神』では、「寿命のろうそくの位置を変えれば助かる」という話が出てくるが、江戸時代の人々も「寿命を延ばす方法」を考えていた。
(1) 食事で寿命を延ばす
- 「養生訓」(貝原益軒) には、健康長寿のための食生活の指南が書かれていた。
- 「粗食こそ長寿の秘訣」とされ、米・野菜を中心とした食事が推奨された。
(2) おまじない・呪術
- 「薬を飲むより、おまじないや祈祷の方が効果がある」と信じられていた。
- 「延命長寿の護符」を寺で買って飲む習慣もあった。
(3) 命を延ばす薬
- 「不老長寿の薬」 という考え方があり、漢方の薬として「人参(高麗人参)」が珍重された。
- 「死神の言うことを聞けば寿命が延びる」という発想も、当時の延命術と共通している。
5. 『死神』の「寿命ろうそく」の発想はどこから来たのか?
- 西洋の「グリム童話」との類似点
- 『死神』の話は、ドイツの「グリム童話」にある 『死神の名付け親』 という話とよく似ている。
- ここでも、死神が「寿命のろうそく」を管理しており、主人公がそれを操作しようとして失敗する。
- 仏教における「命の灯火」
- 仏教では、「人の命は灯火のようなもので、いつか消える」と説かれる。
- ろうそくを寿命のメタファーとして使うのは、日本の宗教観にも合っていた。
死神を聞くなら「三遊亭圓生」
三遊亭圓生の落語「死神」は、独特なユーモアと緊張感が絶妙に交わる物語で、聞き手を最後まで引き込む名作です。人間の生死に対する鋭い洞察が光る一席。

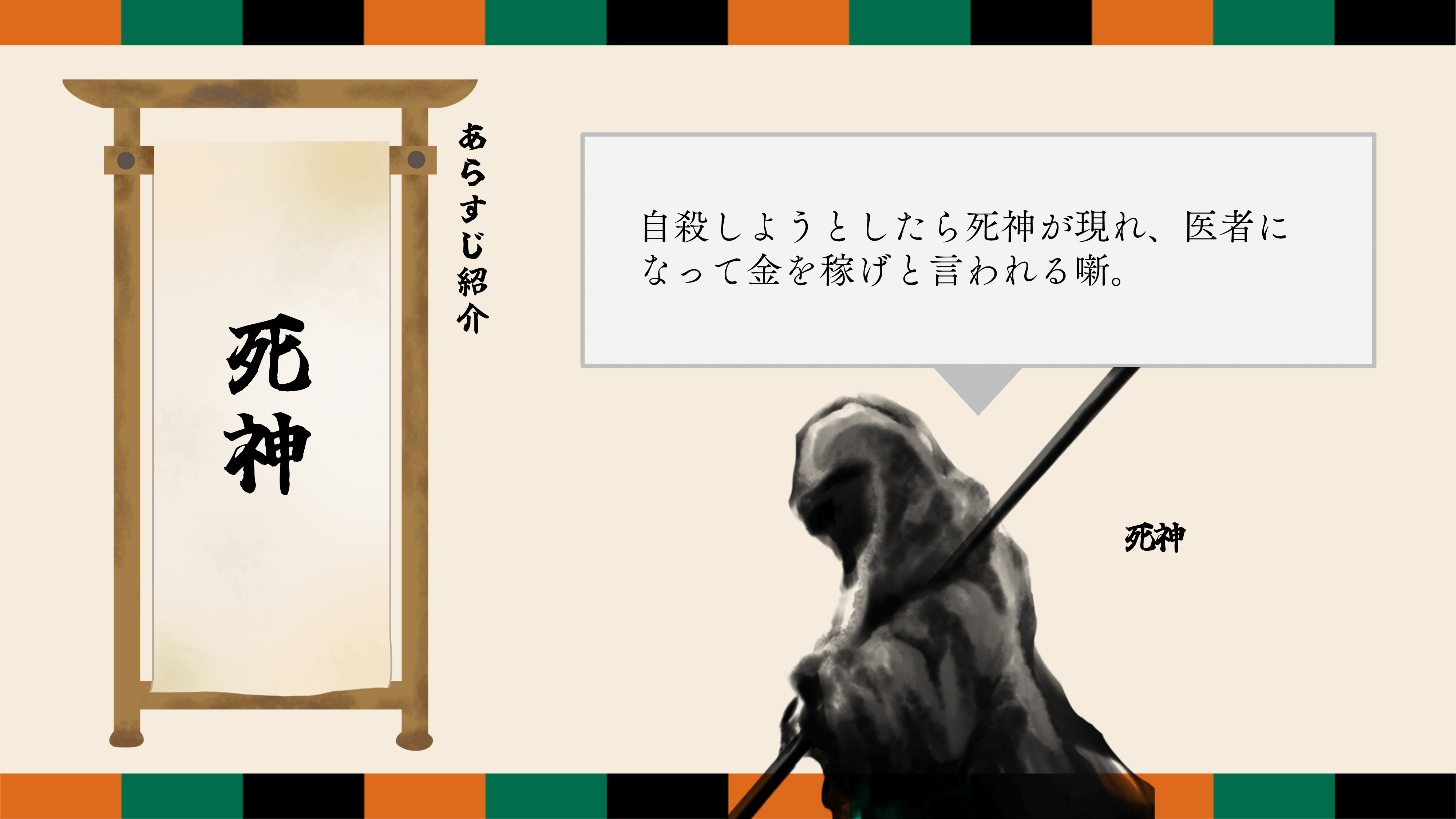





コメント