一言で「鈴ヶ森」を解説すると…

泥棒の見習いが追いはぎの訓練に行き、失敗する噺。
主な登場人物
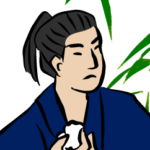
泥棒の親分だ!

新人泥棒をやっております!

新人泥棒に脅しを掛けられた強い男だ!
鈴ヶ森の詳細なあらすじ
見習いの泥棒が、頭(かしら)に連れられて鈴ヶ森での追剥ぎの実地訓練に出かけることになる。
見習いはまだ泥棒としての基礎知識すら身についておらず、頭が教えることにいちいち疑問を持ち、頼りない様子を見せる。頭が鈴ヶ森で追剥ぎをすると告げると、見習いは鈴ヶ森が暗くて怖いと尻込みする。
頭から教わった脅しの決まり文句を覚えようとするが、覚えられずに紙に書いてもらおうとする。しかし、暗い中では書けず、見習い自身も文字が読めないため、相手に読ませるという情けない発想をする。
鈴ヶ森に到着し、見習いは竹藪に隠れるが、筍に尻を突かれてもがく。その間に旅人が通りかかり、頭は見習いをポンと押し出す。
見習いは震えながら脅し文句を並べるが、そのたどたどしい様子から旅人に見破られ、「とうしろう上り、泥棒の前座だな」と揶揄される。
旅人「四の五の言うと首根っこ引っこ抜くぞ」
見習い「やめて、やめて!身ぐるみ脱ぐから勘弁してください・・・」
1. 鈴ヶ森という場所について(歴史・背景)
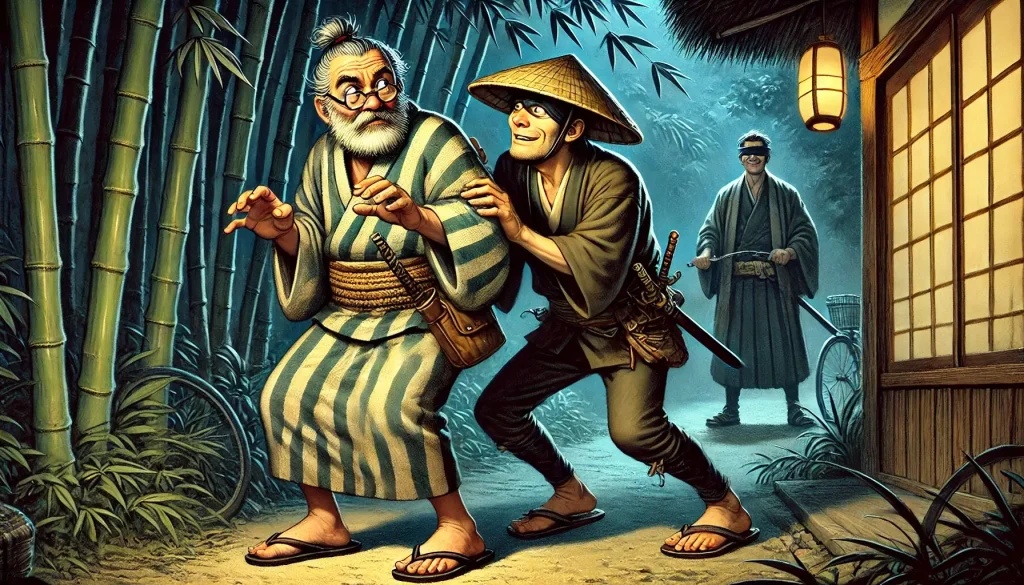
「鈴ヶ森」という名前を聞くと、落語ファンならすぐに「鈴ヶ森の追剥ぎ」を思い浮かべるかもしれません。しかし、実は江戸時代の「鈴ヶ森」は、単なる追剥ぎスポットではなく、江戸随一の刑場として恐れられた場所でした。この記事では、鈴ヶ森の歴史やその恐ろしい過去について詳しく掘り下げていきます。
鈴ヶ森とは? 江戸最大の刑場

画像参照:Wikipediaより
鈴ヶ森(現在の東京都品川区南大井)は、江戸時代の代表的な刑場(処刑場) の一つでした。
この刑場が開設されたのは、慶安4年(1651年)。幕府は、江戸の治安維持と犯罪者の見せしめのために、品川宿の外れにこの刑場を設置しました。
なぜここに刑場が作られたのか?
- 江戸への玄関口(東海道の入口) に近く、人々の目に触れやすい。
- 遺体の処理がしやすいように、近くに海(東京湾)がある。
- 城下町の中心から離れており、臭気や穢れの影響を避けられる。
ここで処刑された罪人の数は数万人ともいわれ、特に磔(はりつけ)や火炙り(ひあぶり)の刑が執行される場所として知られていました。
鈴ヶ森の刑場で行われた処刑の方法
江戸時代の刑場では、犯罪の種類や罪の重さによって処刑方法が決まっていました。
- 磔(はりつけ)
- 罪人を木の柱に縛り付け、槍で突いて処刑する方法。
- 特に凶悪な罪を犯した者に科せられた。
- 有名な磔刑囚には、侠客・幡随院長兵衛を暗殺した水野十郎左衛門 などがいる。
- 火炙り(ひあぶり)
- 火あぶりの刑は主に放火犯に科せられた。
- 江戸時代、火事は大罪だったため、見せしめとして刑場で公開処刑された。
- 放火犯を処刑する際は、燃えやすい油や薪を大量に使い、長時間苦しませるようにした という記録も。
- 獄門(ごくもん)
- 罪人の首を刎ね(斬首)、さらし首にする刑。
- 鈴ヶ森では、処刑後の首を竹槍に突き刺して数日間放置する ことで、罪人への警告としていた。
- 打ち首(うちくび)
- 罪人を座らせた状態で刀で首を斬り落とす。
- 江戸時代の刑罰では比較的よく行われた方法で、幕府の命令による公儀御仕置場(こうぎおしおきば)として鈴ヶ森が使用された。
こうした処刑が行われる場所だったため、「鈴ヶ森」は江戸の人々にとって恐怖の象徴 でした。さらに、刑場があった場所には無数の幽霊話や怪談 が伝えられ、「夜になると罪人の霊が彷徨っている」などと噂されるようになります。
鈴ヶ森と落語「鈴ヶ森」
落語「鈴ヶ森」では、そんな恐ろしい場所を舞台に、ポンコツな見習い泥棒がビクビクしながら追剥ぎを学ぶ…という、まるでコントのような展開が描かれます。
実際、鈴ヶ森は「犯罪者の処刑場」だったため、落語のように「泥棒が盗みを働く場所」としては適していないとも言えます。
しかし、江戸の庶民の間では「鈴ヶ森=怖い場所」というイメージが強かったため、それを逆手に取って「幽霊が出るから怖い」とビビる見習い泥棒」という設定が笑いを生んだのかもしれません。
2. 泥棒の見習い制度について(江戸時代の盗賊組織)
落語「鈴ヶ森」では、泥棒の「頭(かしら)」が見習いを連れて、鈴ヶ森で追剥ぎの実地訓練を行おうとします。しかし、実際に江戸時代にこのような「泥棒の見習い制度」は存在していたのでしょうか?
江戸時代の盗賊団の実態
江戸時代の盗賊は、個人で活動する「渡世人」もいましたが、多くは組織的な盗賊集団として活動していました。
代表的な盗賊団としては以下のようなものがあります。
- 白浪(しらなみ)
- 江戸時代の都市型盗賊集団の総称。
- 主に金持ちの商家や大名屋敷をターゲットにしていた。
- 有名な白浪五人男(日本駄右衛門など)もこのタイプ。
- 夜盗(やとう)
- 深夜に忍び込んで家財を盗む。
- 武士や町人が寝静まった時間を狙い、物音を立てずに犯行を行うのが特徴。
- 追剥(おいはぎ)
- 街道を歩く旅人を襲い、金品を奪う。
- 落語「鈴ヶ森」の泥棒たちはこの追剥ぎに分類される。
- 香具師(やし)
- 表向きは商人や大道芸人として活動しながら、盗賊行為を行う者たち。
泥棒の「見習い制度」はあったのか?
「鈴ヶ森」のように泥棒の「師匠」と「見習い」という関係が実際にあったかどうか について、確かな記録はありません。しかし、当時の盗賊団には以下のような特徴がありました。
- 盗賊集団には「頭(かしら)」がいた
- 盗賊団にはリーダー的存在がいて、「頭(かしら)」と呼ばれることがあった。
- 新入りの泥棒は「丁稚(でっち)」のように雑用をこなしながら、盗みの技術を学ぶこともあった。
- 盗賊には「流派」や「専門技術」があった
- 鍵を開ける技術を持つ「鍵師」
- 壁をよじ登る技術を持つ「忍び」
- 商人の財布を狙う「掏摸(すり)」
- 捕まらないための「教育」はあった
- 「逃げる際のルール」
- 「捕まった時の言い訳」
- 「盗む対象の見極め方」
このように、完全な「見習い制度」ではないが、組織的な盗賊には教育制度があった ことがわかります。

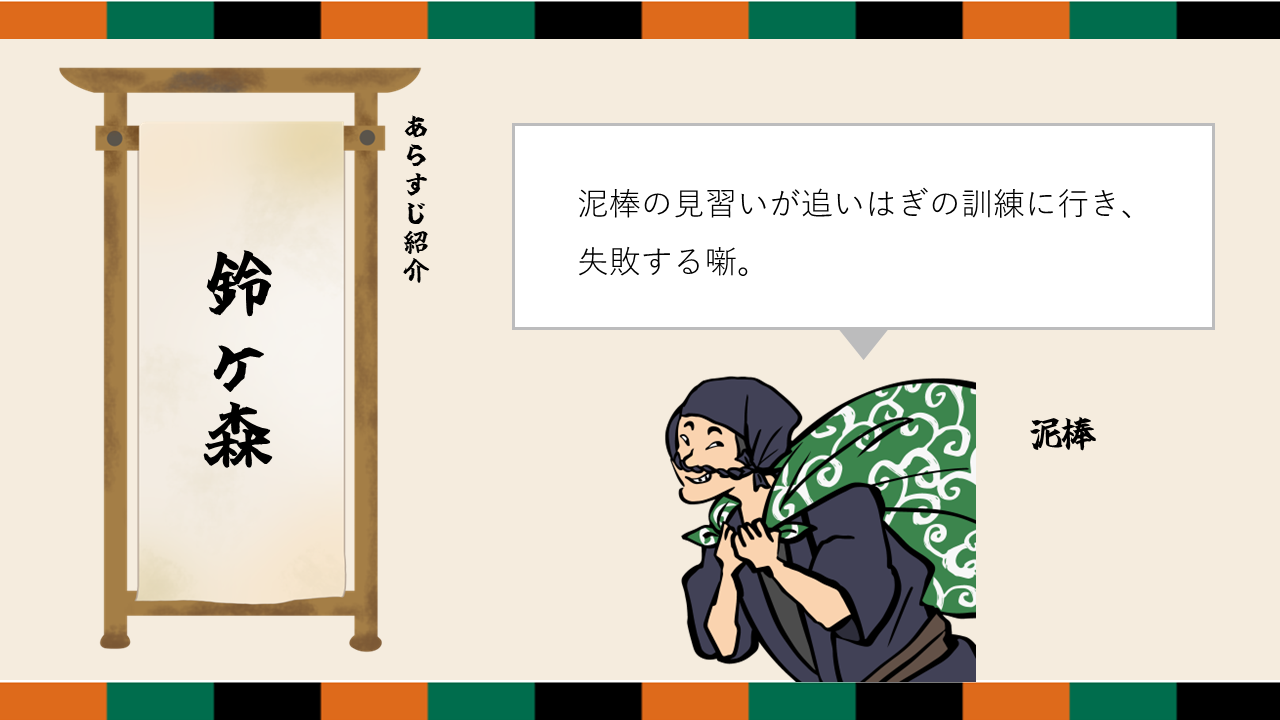



コメント