一言で「崇徳院」を解説すると…

和歌がつなぐ、恋煩いとすれ違いの大騒動から生まれる滑稽噺。
主な登場人物
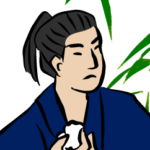
若旦那がもらった手紙を手掛かりに娘を探す男、熊五郎です!

若旦那の様子を心配し、熊五郎に依頼した大旦那です!

20日前に茶店であった娘に一目惚れし、恋煩いをした若旦那です・・・

店のお嬢様が恋煩いし、歌を手掛かりに男を探しにきた男です!
崇徳院の詳細なあらすじ
熊五郎は出入りの店の大旦那に呼ばれ、若旦那の様子を見てほしいと頼まれる。若旦那は気の病で寝込んでおり、原因は恋煩いだった。
20日前、清水の茶店で出会った美しい娘に一目惚れし、別れ際に「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」と書かれた紙をもらった。これは「割れても末に逢はんとぞ思ふ」という崇徳院の歌で、再会を誓うものだった。
大旦那は熊五郎に娘を探すよう依頼し、成功すれば借金を棒引きにし、三軒長屋を与えると約束する。熊五郎は「水の垂れるような美人」を探し回るが手がかりがない。そこで女房の助言を受け、崇徳院の歌を大声で詠みながら人の集まる風呂屋や床屋を巡る。
床屋で通行人に声をかけられ、「娘がその歌を口ずさむ」と聞き喜ぶが、娘はまだ五歳だった。仕方なく探し続け、夕方、再び同じ床屋に入ると、今度は「店のお嬢さんが恋煩いし、崇徳院の歌を手がかりに相手を四国に探しに行く」と言う男に会う。
話を聞くと、互いの探し人が一致することが分かり、「俺の店に来い」「いや、お前の方からうちの店に来い」と言い争いが始まる。言い争ううちに誤って店の鏡を割ってしまい、床屋が弁償を求める。
すると、その男が一言。
男「心配いらねえ、割れても末に買わんとぞ思う。」
崇徳院を聞くなら「古今亭志ん朝」
古今亭志ん朝の『崇徳院』は、テンポの良い語り口と絶妙な間で、江戸っ子の粋なユーモアを際立たせる名演。熊五郎の奔走を巧みに演じ分け、聴く者を物語の世界へ引き込む。品のある話芸で、落語『崇徳院』の魅力を存分に味わえる一席。
『崇徳院』の和歌の背景と意味

この落語のタイトルにもなっている「崇徳院」の和歌は、
「瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の 割れても末に 逢はんとぞ思ふ」 という一首です。
この和歌は平安時代の 崇徳院(崇徳天皇) が詠んだとされ、『百人一首』にも収められています。
和歌の意味
「流れの速い川が岩にぶつかり、二つに割れてしまうけれど、やがてまた合流するように、たとえ離れても最後には必ず再会できると信じている。」
これは 運命的な愛 を表現した歌で、特に江戸時代には恋愛の歌として広く知られていました。落語『崇徳院』では、この和歌が登場人物たちの恋の行方を象徴し、物語の軸となっています。
江戸時代の和歌文化と『崇徳院』
江戸時代の人々は、和歌を単なる詩として楽しむだけでなく、手紙や会話の中で「隠れたメッセージ」として使うことがありました。特に恋愛においては、直接的な表現がはばかられる場面で和歌が用いられました。
若旦那が一目惚れした娘が、別れ際にこの和歌を書いた紙を渡したのは、「あなたと私は今は別れるけれど、またきっと会えますよ」という意味を込めたものだったのです。
崇徳天皇とは?

画像参照:Wikipediaより
崇徳天皇(すとくてんのう、1119年 – 1164年) は、平安時代後期の第75代天皇です。彼は日本の歴史において「怨霊」としての伝説を持つ数少ない天皇の一人であり、その生涯は悲劇に満ちていました。
崇徳天皇の生涯
- 1119年:鳥羽天皇の第一皇子として誕生。
- 1123年:わずか5歳で天皇に即位(崇徳天皇)。
- 1142年:父・鳥羽上皇の意向により、近衛天皇に譲位。
- 1156年:保元の乱が勃発し、崇徳上皇は敗北。
- 1156年以降:四国・讃岐(現在の香川県)に流罪となる。
- 1164年:讃岐で崩御。
崇徳天皇は、父・鳥羽上皇との関係が悪く、譲位後は不遇の時代を過ごしました。保元の乱では自らの勢力を持とうとしましたが、敗北し、最終的には流罪となり、京都に戻ることは許されませんでした。
「日本国の大魔縁」となった崇徳天皇
流刑地の讃岐で失意の日々を送る中、崇徳天皇は仏教に深く帰依し、経典を書き写して朝廷に献上しようとしました。しかし、朝廷側はこれを拒否。この仕打ちに激怒した崇徳天皇は、「我は日本国の大魔縁となり、朝廷に祟りをなす」と呪詛し、爪や舌を噛み切って血で経文を書いたと言われています。
その後、京都では異変が相次ぎ、彼の怨霊が祟ったと恐れられるようになりました。そのため、のちに「崇徳院」として手厚く祀られることとなりました。
和歌と崇徳天皇の関係
崇徳天皇は和歌にも優れ、『詞花和歌集』の編纂に関わり、『百人一首』にもその歌が収められています。
彼の詠んだ「瀬をはやみ…」の和歌は、単なる恋愛歌としてだけでなく、彼自身の波乱に満ちた人生や、都を追われても再び帰りたいという願いが込められているとも解釈されています。

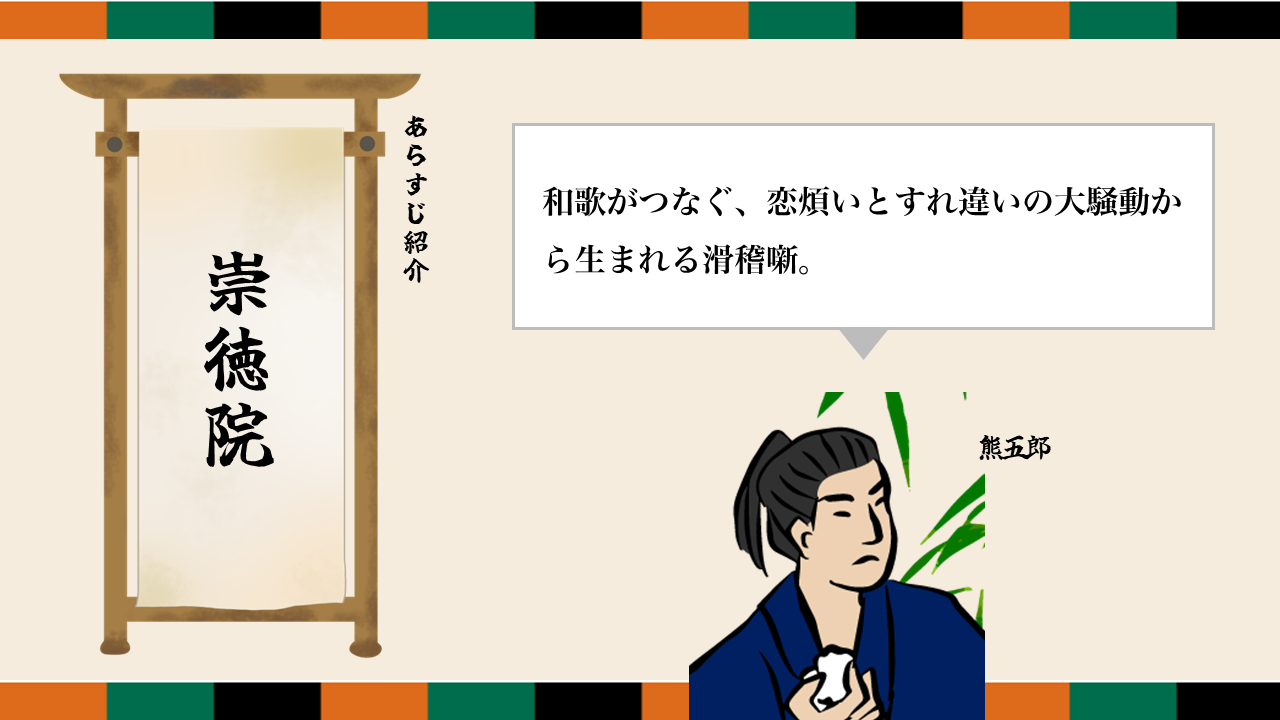



コメント