一言で「目黒のさんま」を解説すると…

はじめて旬のさんまを食べた殿様が、それ以降さんまに恋焦がれてしまう噺。
主な登場人物

はじめて旬のさんまを口にした殿じゃ!

殿の家老を務める田中三太夫です・・・

殿の家来です・・・本当に殿は・・・

殿にさんまを所望された料理人です・・・
目黒のさんまの詳細なあらすじ
晴天の折、殿様の急な提案で、目黒に遠乗りに出かけた殿様一行。途中で殿様が腹を空かせ、家来に弁当を求めたが急なことだったので食べ物は何も用意をしていない。
そんな折、一軒の農家で焼いている秋の旬なさんまの匂いがしてくる。早速家来に買わせ、食す。
初めて食べるさんまの美味しさに感動し、あったさんまをみんな平らげてしまう。屋敷に戻ってもその味が忘れられない。
後日、親戚の家で食べたいものを尋ねられ「さんま」と答える。
驚いた親戚は魚河岸からさんまを取り寄せ、蒸して骨を抜いて出す。
しかし、目黒で食べた味にはほど遠く、殿様は料理人に聞く。
殿様「このさんまいずれより求めた!?」
料理人「房州で取れました本場の秋刀魚にございます!」
殿様「それはいかん、さんまはやっぱり目黒に限る」。
目黒のさんまを聞くなら
目黒のさんまを聞くなら「三遊亭金馬」
古今亭志ん朝が父・古今亭志ん生の他に「習うべき落語」を称した落語家「三代目三遊亭金馬」。余計な演出はせず、老若男女問わず分かりやすい確かな落語が特徴。その落語は楷書で書いたような落語と言われる。
\Amazon Audileで聞けます/
落語『目黒のさんま』は、殿様が庶民の食文化を知らないまま勘違いを重ねる滑稽な話である。この噺をより深く楽しむために、江戸時代の庶民と武士の食文化の違いや、目黒という土地について詳しく見ていこう。

1. 江戸時代の庶民と武士の食文化の違い

画像参照:日本食文化の醤油を知るより
江戸時代の庶民は、基本的に質素な食生活を送っていたが、魚は重要なたんぱく源の一つだった。特に、江戸は海に近いため、新鮮な魚介類が手に入りやすく、焼き魚や煮魚が日常的に食されていた。
一方で、武士や大名の食事は、栄養バランスや品格が重視されていた。特に大名や上級武士の間では、食品の見た目や作法が重要視され、脂っこいものや焼き魚などは敬遠される傾向にあった。殿様がさんまを焼いたまま食べたことに驚くのも、こうした武士の食文化の背景がある。
また、当時の武家では、魚の骨を取り除き、蒸して柔らかくするなどの工夫が施された料理が一般的だった。噺の中で、殿様が「房州のさんま」を蒸して骨を抜かれた状態で食べたとき、「目黒で食べたさんまとは違う!」と不満を漏らしたのは、庶民の素朴な焼きさんまの味が格別だったからだろう。
2. 目黒の地理とその歴史
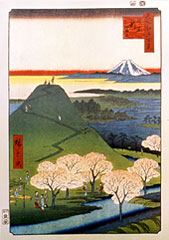
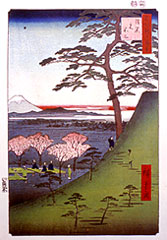
画像参照:目黒区HPより
目黒は現在、東京都の一等地として知られているが、江戸時代には農村地帯であり、武士や町人が遠乗りを楽しむ場所の一つだった。
落語の中で殿様が遠乗りで目黒に訪れたという設定は、実際に武家の間で行われていた娯楽の一環である。馬に乗って江戸の郊外を巡り、自然を満喫することは、城中での生活が長い武士にとって貴重な息抜きとなった。
また、目黒には『目黒不動尊』(瀧泉寺)などの名所があり、庶民にとっても憩いの場であった。そうした背景から、農家が焼く秋刀魚の香ばしい匂いが殿様の食欲をそそったという描写も、当時の目黒の環境を考えるとリアリティがある。
3. さんまの流通と価値
江戸時代のさんまは、現在のように全国各地から輸送されるものではなく、主に近海で獲れたものが江戸の市場に並んでいた。特に、房州(現在の千葉県南部)や伊豆(静岡県)の沖合で獲れるさんまが多く、江戸の庶民は手頃な価格で楽しんでいた。
対して、武士や大名の食卓に並ぶ魚は、高級魚や調理に手間のかかるものが中心だった。さんまのように脂が多く、大名にとっては食べ慣れない魚は、通常の献立には含まれなかった。
しかし、目黒で食べた庶民風の焼きさんまが気に入った殿様が、後日同じ味を求めたものの、武家の食文化に適応された調理法で提供され、違和感を覚えたというのが『目黒のさんま』の面白さの一つである。

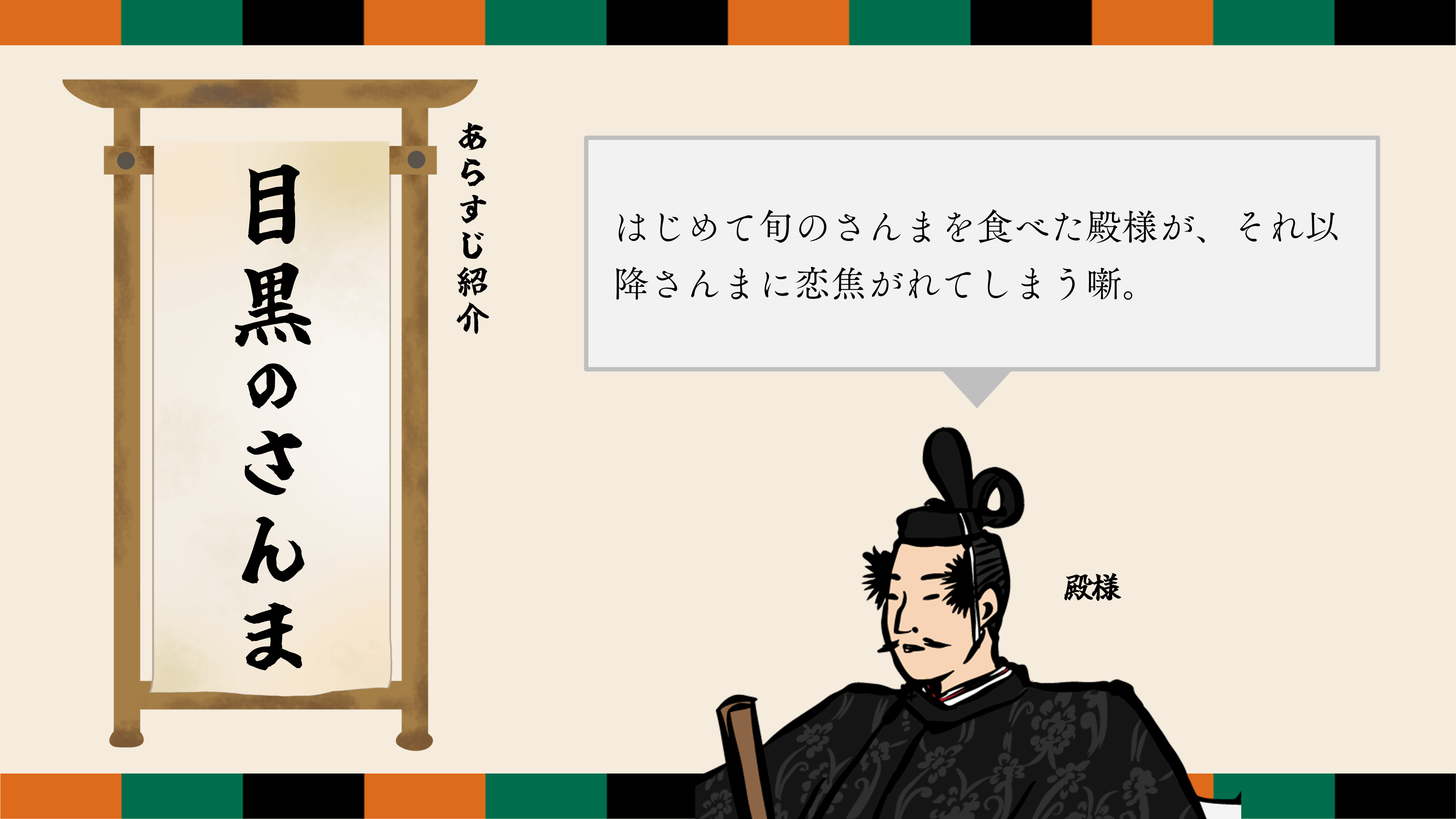




コメント