一言で「二番煎じ」を解説すると…

堅物で真面目な倅の時次郎が、騙されて吉原に行ってしまう噺。
主な登場人物

火の回りの月番をしている旦那です
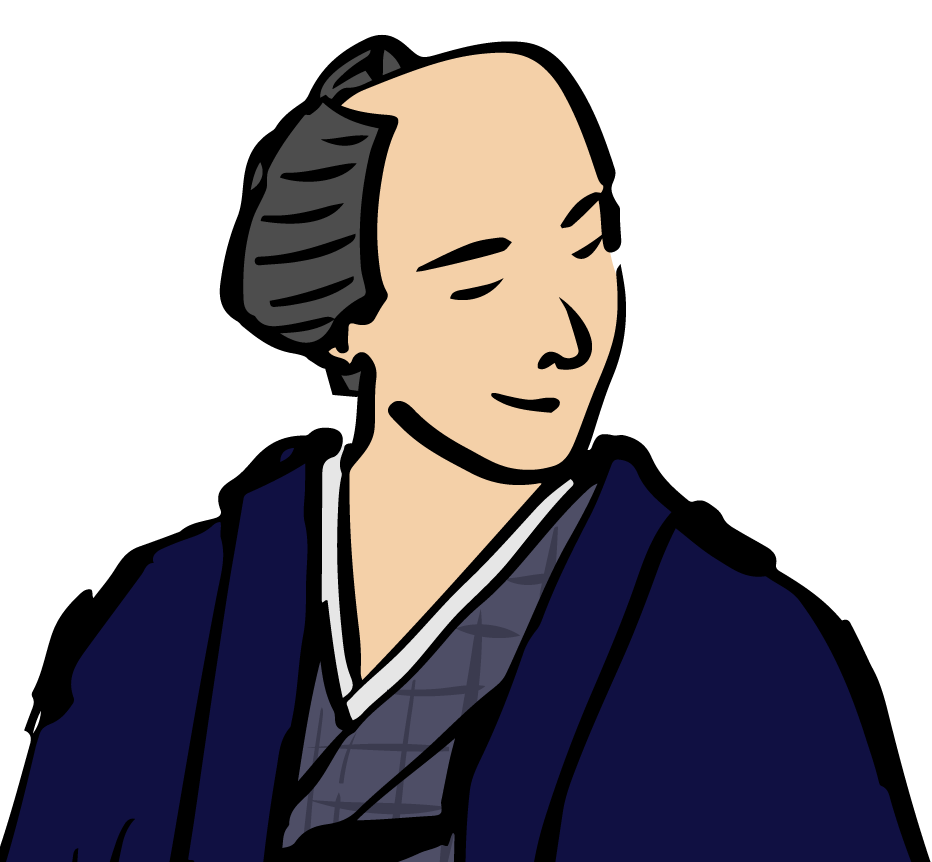
火の回りにお酒を持ってきた黒川先生です

獅子の肉を持ってきた宗助です!

火の回りがちゃんとされているか、見回りに来た役人だ!
二番煎じの詳細なあらすじ
江戸では町内の夜回りは番太郎に任されていたが、酔っ払いや寒さで怠けることが多く、旦那たちが夜回りをすることになった。
寒い夜、旦那たちは番屋で休むため、二手に分かれて夜回りを行うことに。
宗助さんは提灯を持たされ、第一陣の夜回りに出発する。寒さのため、拍子木や金棒の音も鳴らさず、「火の用心」の掛け声も様々な調子で出される。
夜回りが終わり、番屋に戻ると二組目が出発。月番は宗助さんに火鉢の炭を増やすよう指示し、旦那たちは体を温めるために酒を持ち込み、鍋を囲んで酒盛りを始める。
皆、寒さからすぐに酔いが回り、楽しんでいる。
そこへ町役人が見回りに来る。慌てた旦那たちは猪の鍋を隠そうとするが、役人は土びんの中身や鍋をしつこく尋ねる。
月番は宗助さんが風邪を引き、その煎じ薬だと誤魔化すが、「良い煎じ薬だ」と言い、役人は酒を飲んでしまう。
最終的に旦那たちは自分たちの酒がなくなるのを防ぐため、役人に「もう煎じ薬はない」と告げる。
役人が一言。「拙者がもうひと廻りしてくる間、二番を煎じておけ・・・」
二番煎じを聞くなら
二番煎じを聞くなら「古今亭志ん朝」
古今亭志ん朝が演じる「二番煎じ」は、その粋でリズミカルな語り口が特徴です。彼の滑らかな語りと調子の良いリズムは、聴く者を自然と引き込みます。志ん朝の「二番煎じ」を聴けば、その場の情景が目の前に広がり、まるで自分も物語の一部になったかのように感じられます。
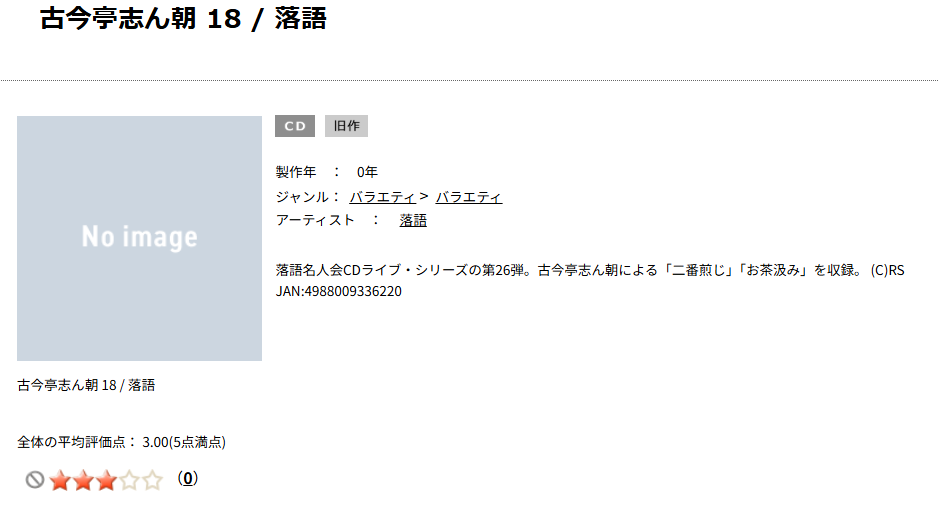
画像引用:TSUTAYA DISCASより
落語『二番煎じ』は、江戸の町内の防火対策や冬の風情、そして旦那衆の人情が垣間見える噺です。この物語をより奥深く理解するために、以下の点を掘り下げて記事のボリュームアップを図りましょう。
1. 江戸時代の夜回り制度とは?

江戸の町では火事が頻発し、特に冬場は空気が乾燥していたため、火の用心が重要視されていました。そこで町ごとに「夜回り」が行われ、町内の安全を守る役割があったのです。
- 夜回りの役割:拍子木を打ち鳴らしながら「火の用心!」と掛け声をかけて巡回
- 担当者:通常は「番太郎」と呼ばれる専属の者が行うが、怠けることが多かった
- 旦那衆の参加:番太郎が信用ならない場合、町内の旦那衆が交代で夜回りを担当する
本作では、怠けがちな番太郎に代わり、町の旦那衆が自主的に夜回りをすることになります。しかし、やはり寒さには勝てず、番屋での酒盛りが始まってしまうのが本題です。
2. 猪鍋と酒盛りの文化

物語の中で旦那衆は、夜回りの合間に番屋で鍋を囲み、熱燗を飲みながら体を温めます。
- 猪鍋(しし鍋):江戸時代は肉食がタブー視されていたが、獣肉は「薬」として食べることが許されていた。特に猪肉は「山鯨(やまくじら)」と呼ばれ、滋養強壮に良いとされた。
- 酒の持ち込み:番屋は本来、飲酒をする場ではなかったが、寒さ対策と称して酒を持ち込むことがあった。これは当時の庶民の知恵でもある。
この猪鍋と酒が、後に役人の目に留まり、物語のオチにつながっていきます。
3. 町役人の見回りと江戸時代の規律
旦那衆が酒盛りを楽しんでいるところへ、町役人が見回りに来ます。本来、役人の仕事は町の治安維持ですが、彼らもまた庶民の生活に馴染んでいることが描かれます。
- 町役人の存在:江戸の町には火付盗賊改、町奉行、同心などの役職があり、火事や盗賊に備えた見回りが日常的に行われていた。
- おとがめなしの理由:この話では役人が猪鍋の匂いに気づき、煎じ薬と称して酒を勧められます。役人は、それを知りながらも共に酒を飲み、「二番を煎じておけ」と冗談を言う。これは、庶民と役人との絶妙な距離感を描いており、厳しい規律の中にも融通が利く江戸の風情を感じさせる場面です。
4. 「二番煎じ」という言葉の意味
落語のタイトルにもなっている「二番煎じ」は、本来「茶の二度目の煎じ直し」を指します。
- 転じて「新鮮味がなくなったもの」「前例の繰り返し」といった意味を持つようになった。
- 本作では、町役人が「もう一度酒を煎じておけ」と洒落を効かせたセリフとして使われている。
このオチによって、ただの火の用心の話ではなく、江戸の庶民と役人のユーモアや人情が際立つ噺になっています。
二番煎じを聞くなら「古今亭志ん朝」
古今亭志ん朝が演じる「二番煎じ」は、その粋でリズミカルな語り口が特徴です。彼の滑らかな語りと調子の良いリズムは、聴く者を自然と引き込みます。志ん朝の「二番煎じ」を聴けば、その場の情景が目の前に広がり、まるで自分も物語の一部になったかのように感じられます。
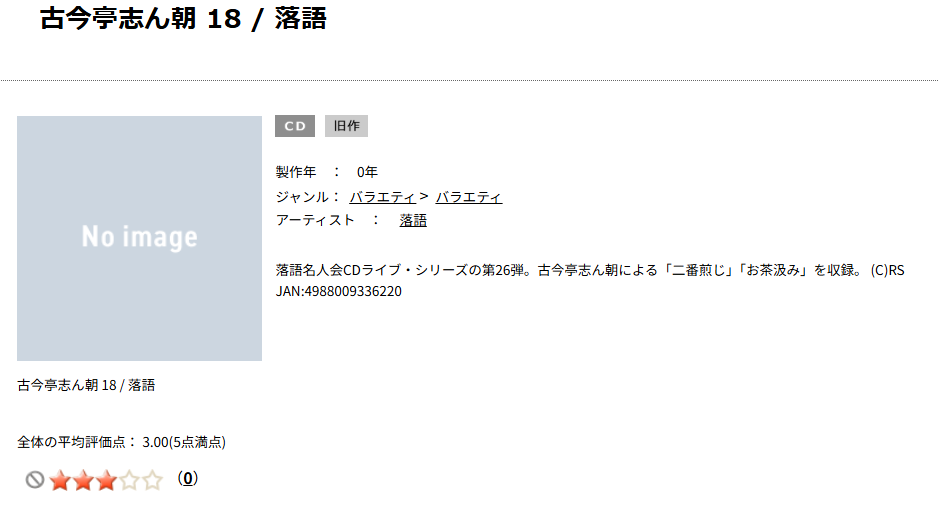
画像引用:TSUTAYA DISCASより

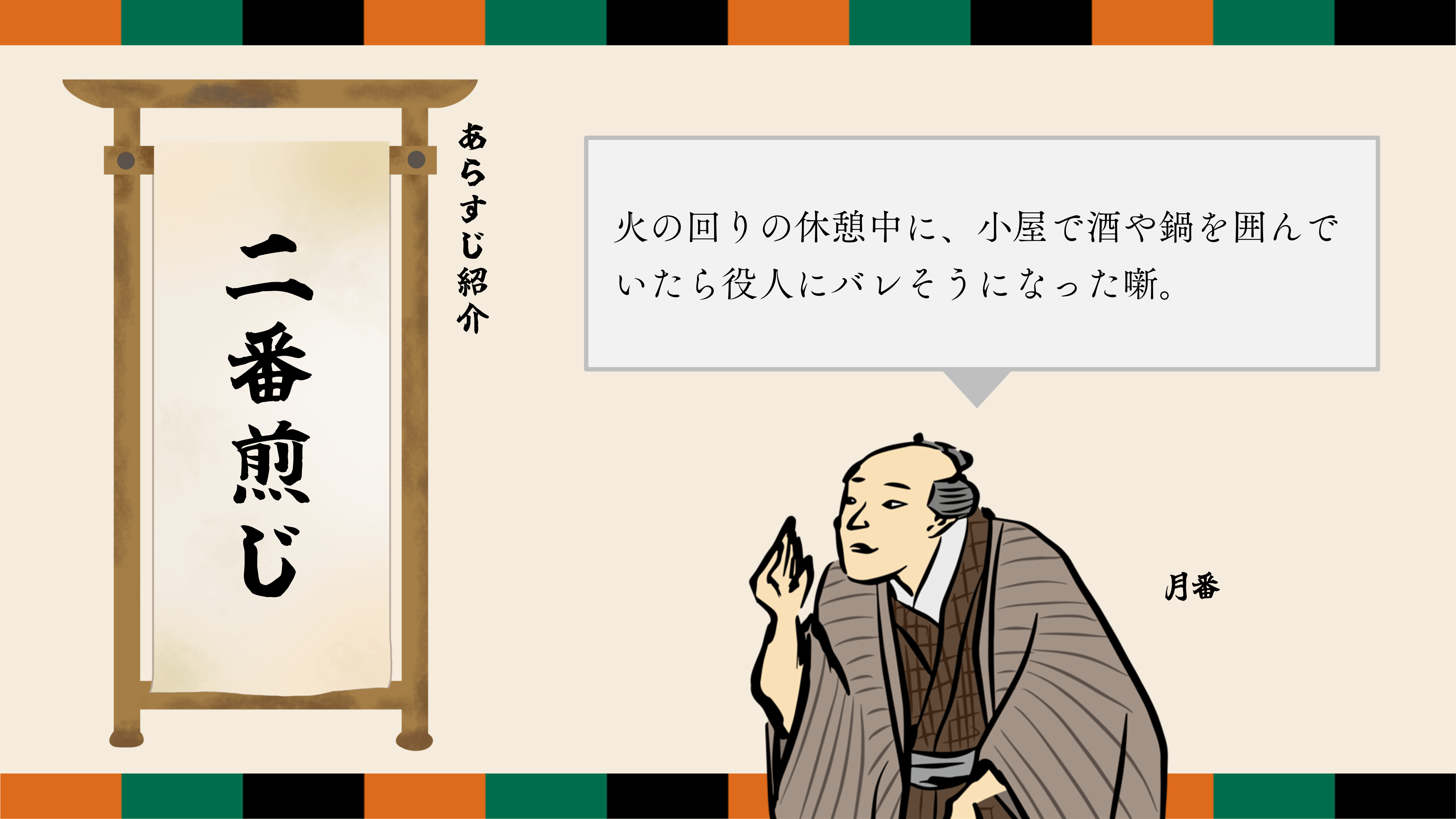



コメント