一言で「時そば」を解説すると…

蕎麦の勘定の間に時を聞いてちょろました詐欺を真似しようとして失敗する噺。
主な登場人物

蕎麦屋です・・・
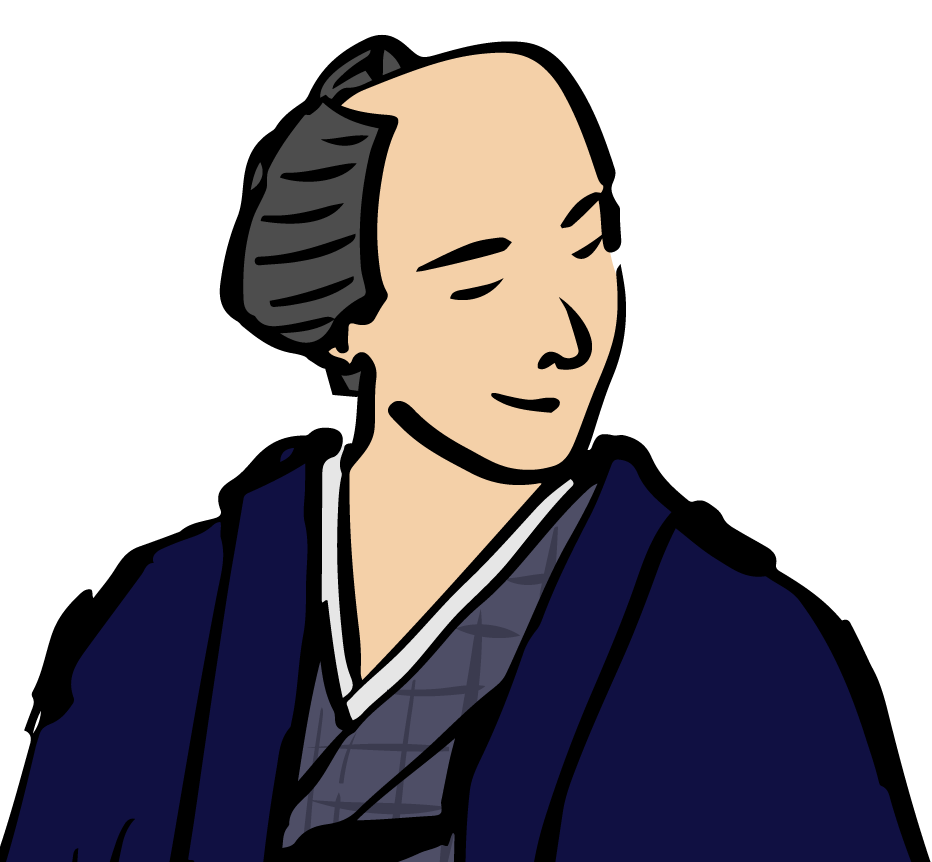
蕎麦の勘定の間に時を聞いて、金をちょろまかした男です!

男を見ていた与太郎です!真似をしたら失敗しました!
時そばの詳細なあらすじ
「夜鷹そば」の二八そば屋を呼び止めた男が、「寒いねぇ、何が出来る」と尋ね、しっぽくそばを注文する。そばを褒めちぎりながら食べ、いざ勘定となる。
そば屋:「十六文で」
男:「銭は細かいよ、手を出せ」と言い、「一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ」と銭を手の平に乗せる。「今、何刻でぇ?」
そば屋:「九つで」
男:「十、十一、十二…」と数え、さっと去ってしまった。
これを見ていた別の男が翌晩、同じ手口を試そうとそば屋を捕まえる。
男:「寒いねぇ」
そば屋:「今夜はだいぶ暖かで」
そばの出来が悪いと文句を言いながらも、目的は食べ物ではない。いざ勘定となり、
そば屋:「へい、十六文で」
男:「小銭は間違えるといけねえ。手を出しねえ、それ、一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ…今、何刻でぇ?」
そば屋:「四ツで」
男:「五つ六つ七つ八つぁぁ・・・」
時そばを聞くなら
時そばを聞くなら「柳家小さん」
三代目柳家小さんが上方の時うどんを江戸噺として移植したのが「時そば」。その後、五代目柳家小さんの十八番として演じられ、人情味あふれる演技で、江戸時代の風情と笑いをたっぷり楽しめます。
\Amazon Audileで聞けます/
※フルは↑の赤いボタンから1か月間無料でご視聴頂けます。
「時そば」と江戸のそば文化

落語「時そば」は、手際の良い男がそば代をごまかす話ですが、背景には江戸時代のそば文化 が深く関係しています。
「時そば」の舞台となる夜鷹そば屋、二八そばの値段、江戸の時刻制度を詳しく解説していきます。
1. 江戸時代のそば文化とは?

参照:コトバンクより
江戸時代、そばは庶民の間で大人気の食べ物でした。
特に屋台そば(夜鷹そば) は、忙しい江戸っ子にとって欠かせない存在でした。
● そばが江戸で人気になった理由
- 手軽に食べられる:立ち食い屋台でサッと食べられる。
- 消化が良い:胃に優しく、夜食にも最適。
- 栄養がある:そばにはビタミンB1が含まれ、脚気予防にも効果的とされた。
➡ 「そば=江戸っ子のファストフード」だった!
2. 「時そば」に登場する「二八そば」とは
「時そば」のそば屋は 「二八そば屋」 と呼ばれています。
「二八(にはち)」の意味には2つの説があります。
- 「そば粉8割、小麦粉2割」
- 現代のそばと同じく、小麦粉を少し混ぜた方がつながりやすく、打ちやすい。
- そばの風味を楽しめる割合として好まれた。
- 「そば一杯16文(2×8=16)」
- 「時そば」に出てくるそばの値段が16文 なので、こちらの説が落語には合っている。
➡ 「二八そば」は、江戸時代の庶民の食べ物として親しまれた!
3. 江戸時代の「16文」ってどれくらいの価値
そば一杯16文が、江戸時代の物価と比べて高いのか安いのかを考えてみましょう。
- そば一杯:16文
- 天ぷらそば:40文
- うなぎの蒲焼:100文
- 一日の人足賃金:400文
- 風呂屋の入浴料:12文
- 米一升(約1.8kg):100文
➡ そば一杯は現代でいう「牛丼1杯」くらいの価格! ➡ 「時そば」は16文を巧みにごまかす話だから、額としてはちょっとした節約レベル。
4. 江戸時代の時刻制度「九つ」とは?
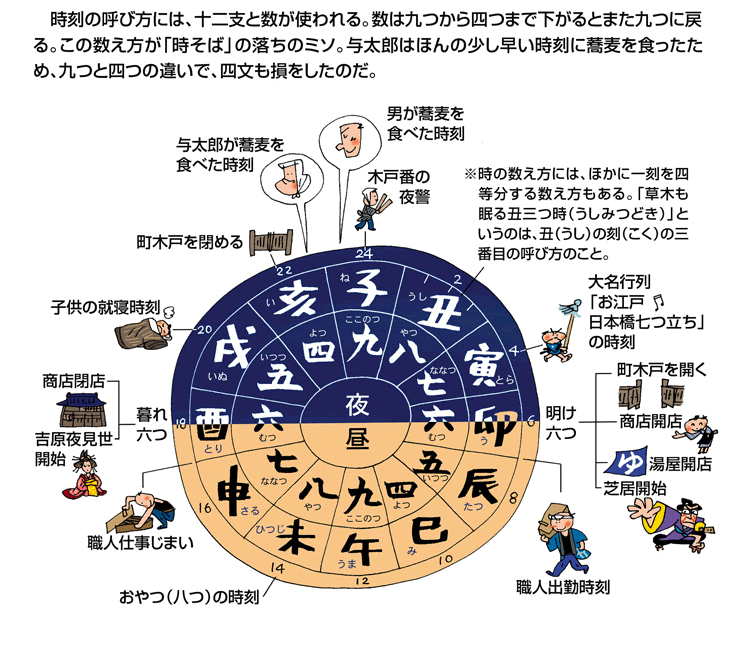
参照:お江戸の科学より
「時そば」の面白さは、江戸時代の時刻制度を利用して支払いをごまかす ところにあります。
● 江戸時代の「不定時法」
- 現在の「午前9時」「午後3時」のような定時制ではなく、1日を昼6刻・夜6刻に分ける 「不定時法」だった。
- 「九つ」「四つ」といった時刻の呼び方があり、季節によって時刻の長さが変わる。
- 「九つ(ここのつ)」=現在の午後8時頃。
- 「四つ(よつ)」=現在の午後10時頃。
➡ 「今、何刻でぇ?」と聞くことで、そば屋に数をカウントさせて支払いをごまかすトリックを生み出した!

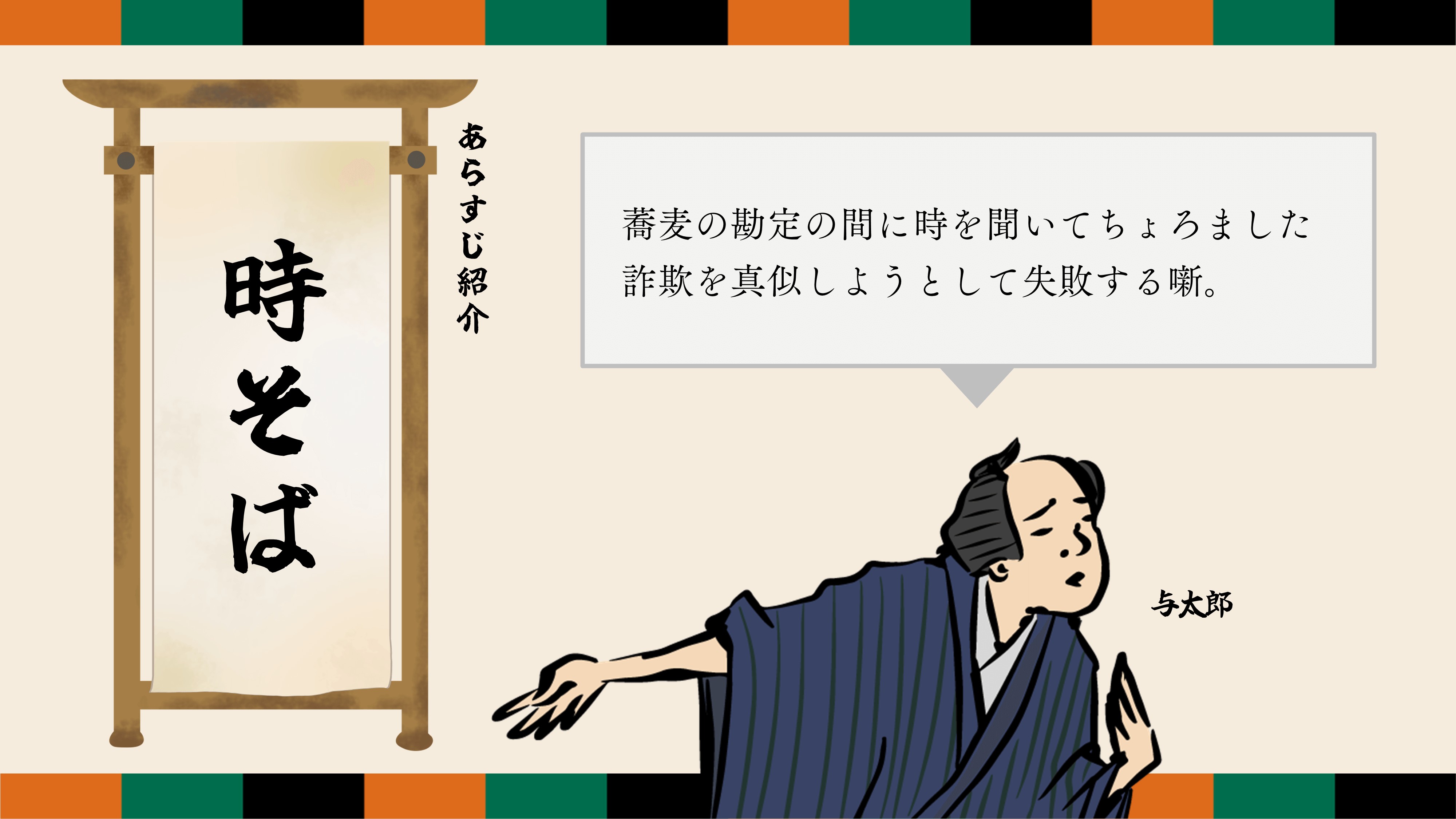




コメント